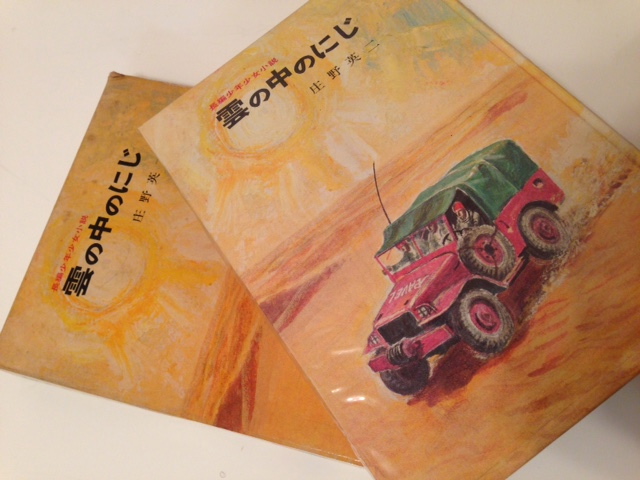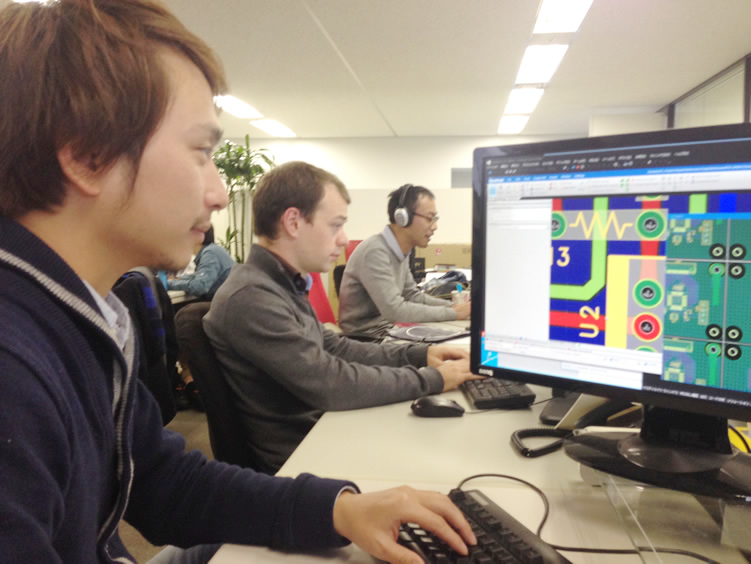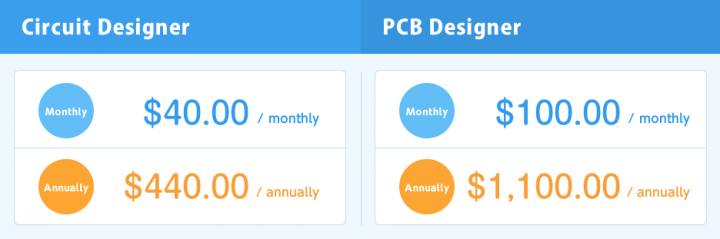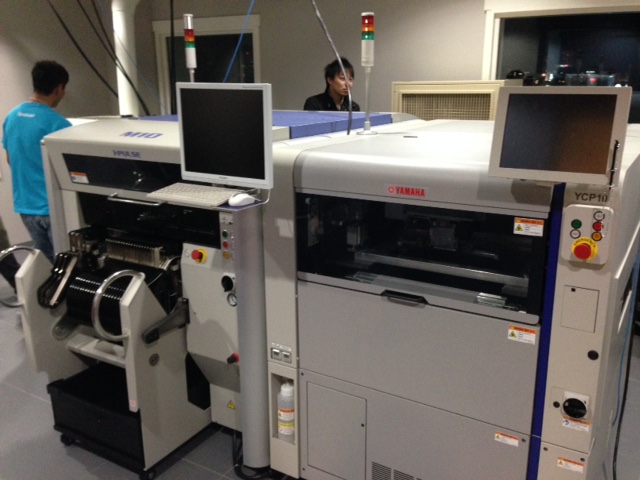・
ハフィントン・ポストのある記事を読んだ時に、ちょっと「あれ?」となったので書いておきます。
人気ランキング上位の日本企業に就職して一生安泰に過ごせると考えているのなら、今すぐ考えを改めた方がいい(Huffington Post)
この記事、「グローバルキャリア」が大切であることと結びつけられていますが、その理由として日本市場がシュリンクし、世界の中でのプレゼンスが低下すること、インターネット等によるグローバル化が進むということ、想定外のことが起こることが普通の世の中になっている、ということが挙げられていますが・・・
全て当たり前のことですよね。
この記事の筆者はアパレル業界の親分であるワールドの執行役員であり、これまでのキャリアを見ると米国生まれで外資系企業の第一線を渡り歩いて来られた方なので、その辺りの事情は熟知されておられるはずですが、今の学生を見て、あえてこの「当たり前」のことを伝えなければならないと危機感迫られて書かれたのであれば、学生(あるいは教育)が、かなり深刻な問題を抱えていると言えそうです。
「グローバルキャリア」とは読んで字の如く、グローバル社会での経歴や職業という意味ですが、グローバルキャリアを目指せと言われた時に学生さんは具体的に何を行わなければならないのでしょうか。語学は必須スキルとしたとしても、じゃあ、外資系企業に就職すれば良いのか、日本企業に就職すれば良いのか意見は別れるところです。
仮に外資系企業に就職したとしても、それが中国籍なにか韓国籍なのかアメリカ籍なのかによって変わるだろうし、外資系企業の日本法人(あるいは日本支社)に就職したとしても、彼らの目的は日本でビジネス展開(グローバル市場の中での one of them)をするために日本に進出している訳であって、そこに就職したとしても、日本で骨を埋めることなってしまう可能性も大いにあります(上司は外国人であることも多いけれど)。逆に日本企業でも、大中小零細問わず、海外売上の方が国内売上を上回っている会社もたくさんあるので、要は「自分の目的」に応じて企業を選ぶこと、選んだ会社で「グローバルキャリア」(と呼ばれるもの・・・)を目指せるかどうかが条件になりますね。必ずしも、海外に出たり、外資系に就職するだけでは不十分ということです。
どんな仕事をしていてもどんな会社に就職しても、能力がある人間は重宝されるものです。「能力」とは、どんな仕事をしても必ず結果を出せる力とでも定義できるかもしれませんが、グローバルキャリアを目指そうが目指さまいが、「能力」のある人間はおのずと自ら生きていく道を選択し、より高みを目指すために幾つもの会社を渡り歩いたり起業したりしてキャリアチェンジをしていくでしょう。語学が必要であれば語学も習得するでしょうし。
「どこぞの企業に就職すれば一生安泰である」というのは、せいぜい戦後の高度成長期のみ通用した訳であって、もう何十年も昔から、もはやその考え方は誰にとっても幻想にしか過ぎないと思うのです。アメリカの大企業であろうが日本の大企業であろうが、潰れる時は潰れるし、シェアが低下してシュリンクするし、マージされるし、企業が存続していても本人が仕事が出来ないならリストラされる。その可能性はドメスティックであろうがグローバルであろうが関係ないと思うのです。
だからこそ「一生安泰」なんて言葉は世の中のどこにも存在しない。もし仮に、今の学生(社会人も含む)の中で、まだそんなことを思っている人がいるとすれば、それはにわかに信じられないことだし、あえてその考え方に警鐘を鳴らす必要があるのだとしたら、これはちょっとした驚きです。
いつの時代も必要なのは、どこであろうが結果を出せることを目指して成長し、生活力や生命力も含めて「強い個」になることが重要ですよね。それが個でなく、チームや組織であったとしても「強くある」のは言うまでもありません。もちろんこの記事に書かれていることは正しいのですが、なんだか少し驚きと違和感を感じてしまいました。