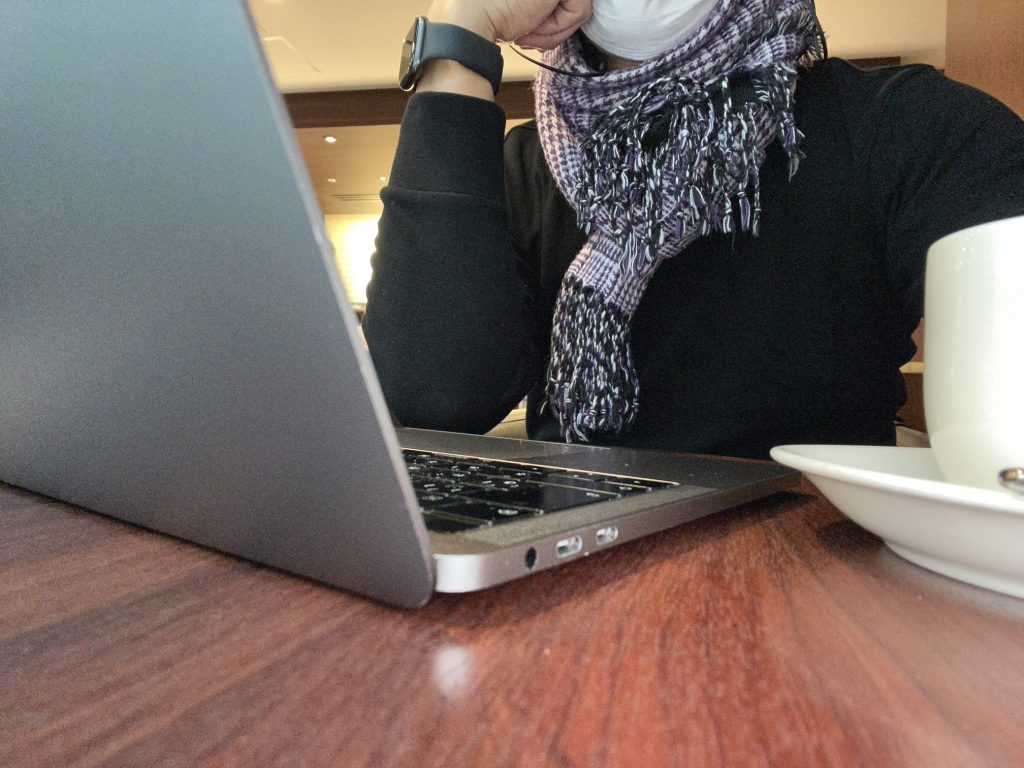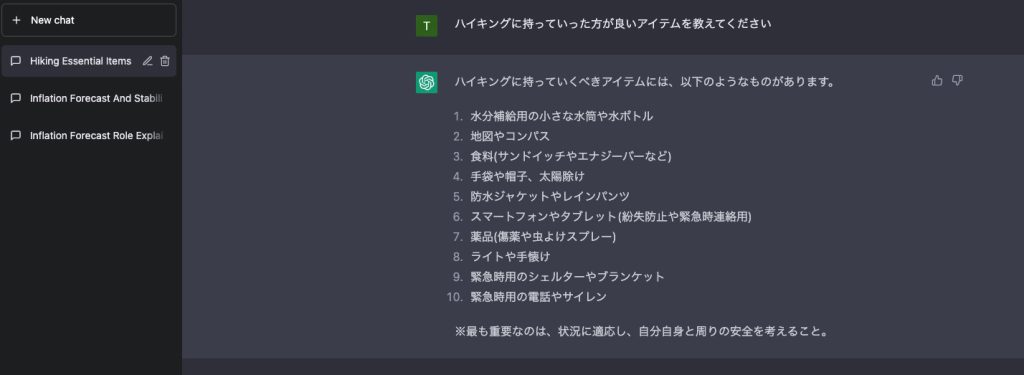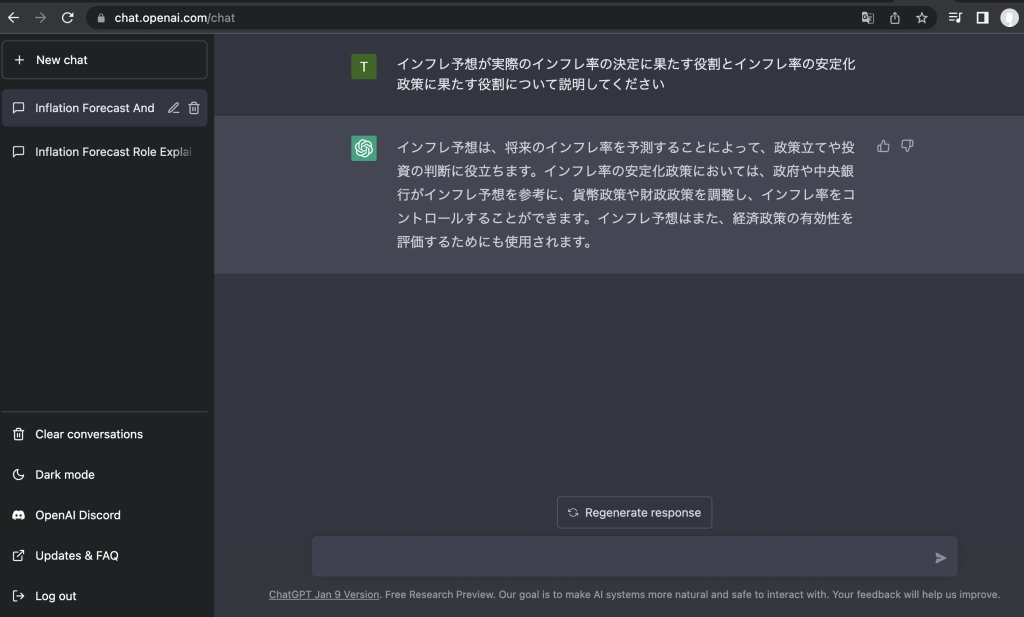「先達」(せんだつ)とは、先にその分野に進み、業績・経験を積んで他を導く人のことを指す言葉です。(weblio参照)元々は修験道の行者が修行のために山に入る際の指導者のことですよね。それが転じて、ある分野において他の人よりも先行し、業績や経験を積んで後進を導くことや、導く人のことを指すようになったようです。
僕は図書館が好きで、週に一度は本を借りに行ったり、自習室で調べ物や仕事をしたりするのですが、その際、膨大な本の数を見て「先達」という言葉を思い出します。図書館にはありとあらゆる分野の書籍が並んでいます。それぞれの分野ごとに必ず「先達」と呼ばれる人が存在し、先行研究がなされ、後進がその先行研究の上に更に研究を重ねていく。その積み重ねが人間の歴史であり、本の数として表れているんだろうなと思うのです。もちろん、本として残らなくても、口伝として伝えられているものもたくさんあります。
同じような意味で、論文検索で有名な Google ScoLar の検索ボックスの下に「巨人の肩の上に立つ」(standing on the shoulders of Giants)という一文があります。
この言葉は「先人の積み重ねた発見に基づいて何かを発見すること」というメタファーで、17世紀のアイザック・ニュートンが言ったという説もありますし、12世紀の哲学者ベルナールの言葉という説もあるようです。歴史に名を刻んだ研究者から名もなき研究者まで、彼らよりも過去に生きた先人たちを、ニュートンやベルナールですら「巨人」と呼んでいることに悠久の時の流れを感じます。
人間の歴史というのは、無数の発見と研究の積み重ねで、それぞれの時代を生きた先人たちの努力の一つひとつの上に、今、自分たちが生きている。それゆえ、自分たちも次の世代のために積み上げ、バトンタッチをしていかなければならないということなんでしょうね。それは研究者じゃなくても、今生きているすべての人に対して言えるのだろうと思います。
たまに、自分が「分かったような気持ち」になったりすることがありますが、図書館の膨大な書籍の数を前に、自分は何も知らないし、何も分かっていないんだろうな・・・と思うと、謙虚な気持ちになります。謙虚さ、大切ですね。それに日々の生活は確かに忙しいのですが、効率的、とか、即効性を求めて情報のつまみ食いをするのではなく、時間を掛けること、回り道すら楽しむこと、むしろ回り道が一番の近道と考えて日々を過ごして行きたいと思います。
図書館、いいですよ。
子供からお年寄りまで、熱心に本を読んでいる姿は尊いな、と感じます。
生きるということは学ぶということなんでしょうね。