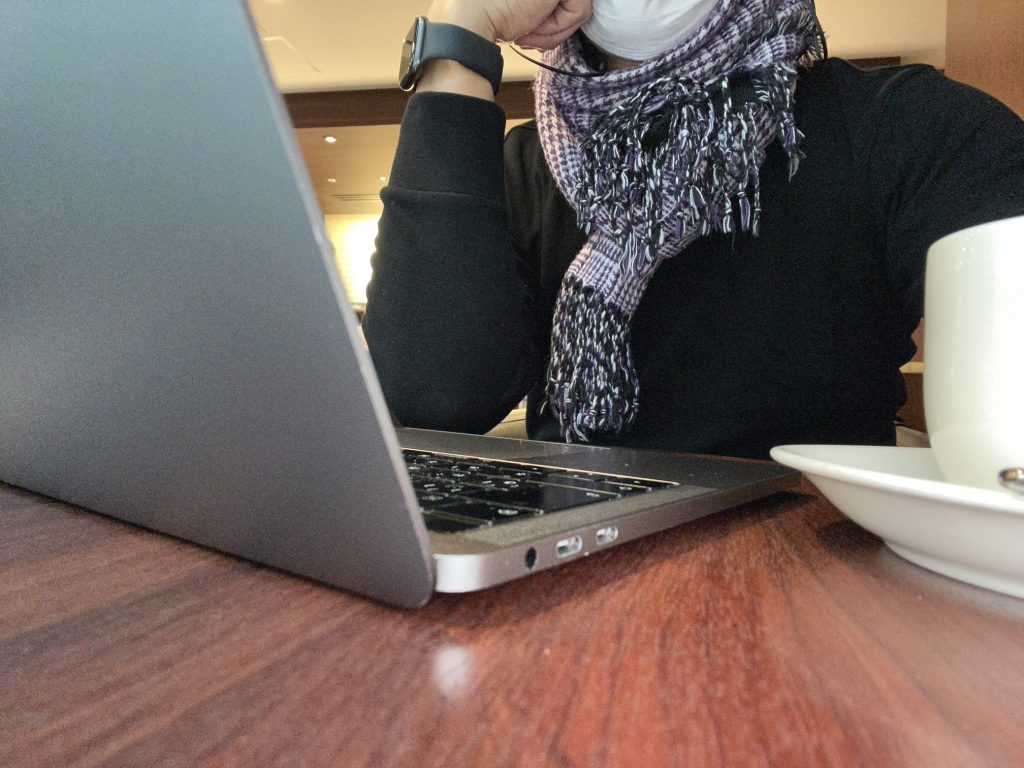12月に入りました。2024年も残り一ヶ月ですね。今年の振り返りは年末に行うとして、最近感じていることを書いてみます。
「古い価値観」「新しい価値観」という言葉を最近よく耳にします。
新しい価値観って一体なんでしょう。それは日頃の生活の中で感じている「大切なこと」や、世の中に対して抱く違和感の中から自然に生まれてくるもので、それが今までの「当たり前」でない場合に「新しい価値観」と呼んで良いのではないでしょうか。日頃感じる違和感を言語化するのは難しいですが、今までのやり方では通用しなくなってきているな〜と思うことや、無理なものは無理と諦めたら良いのに〜と思うことが多々あります。
例えばビジネスの世界では、顧客の要望に答えることが当たり前とされてきましたが、そもそも顧客のレベルが低ければ、その要望にいくら応えようとしても改善は生まれません。このような場合、顧客の要望を否定し、新しいあり方を提案し、啓蒙していくことの方が顧客のためになります。これが比較的新しい価値観かもしれませんし、そういう動きが良く見られるようになりました。
また、業務効率化や生産性向上というキーワードが巷に溢れていますが、これにも違和感を感じる人が増えています。そもそもモノやサービスが飽和した社会において、財をスピード速く大量に生産し、市場に投入することになにか意味があるのか?それで喜ぶのは雇用者報酬を削減し、営業余剰を生み出すことが自分のメリットになる経営者や株主などの資本家だし、生産速度を向上させてもモノが売れないのであれば、過剰在庫が生まれ、供給過多で失業増加につながることが簡単にイメージできます(マクロ経済学の話になってしまいました)。ですから、本当に必要なものを、必要なだけゆっくり作る、値段が高くなっても、それが環境にも人体にも良いのであればそれでいい、これも新しい価値観かもしれません。
僕の場合、こういった考えの原点にあるのは、そのやり方で社会は良くなりましたか?結果、出てます?という問いなんですよね。たとえば、効率性を追求する → 業務効率が2倍良くなれば、同じ労働時間で給料2倍になるはずですが、なってますか?あるいは、週5日働いていたのを、同じ給料をもらいながら2.5日に短縮できるはずですが、なってますか?ということです。
根本的に、今までのやり方を継続しても意味がないことって世の中にはたくさんあります。それは組織開発の分野でも同じで、100点満点の組織開発手法があれば、組織に関わる様々な問題は存在しなくなるだろうということですが、そうはなっていませんよね。また逆に、そういった研修やコンサルを提供している会社の方こそ離職率が高かったり、そもそも儲かっていなかったりすることが多々あります。ITの分野でも、OSやサーバがバージョンアップしてERPなどのシステム更改をして改悪、何百億円損失、個人情報流出、なんてこともザラです。何やってるんだろう?まさにここにビジネスの肝が存在します。答えのない(結果がでない)問題が存在し続けるからこそビジネスが成り立ち、問題がなければ、わざわざ問題を作ってワーワーやることが「古い価値観」のビジネスなんです。
物がない時代は、まず住む家、食べる物、着る物を充足させるために、人々は一生懸命働きました。産業革命から始まる技術革新、重工業の時代、二つの大戦を経て、日本では高度成長期を迎え、オイルショックやインフレなどを経験しながらも、1980頃までは年10%程度の経済成長をしてきました。先人たちのがんばりのおかげで、物質的に豊かになり、物が充足しましたが、今はどうでしょうか。
主要先進国の平均GDP成長率は、1960年代には5.5%でしたが、1980年代には2.96%、2010年代には1.06%になっています。つまり、経済成長は下降トレンドにあるということが誰の目で見ても明らかです。この間に、インターネットの普及やエネルギー革新があったにも関わらずです。(2019年にノーベル経済学賞を受賞したバナジーとデュフロが「インターネットが経済成長をもたらしたということを示すデータは一切存在しない」と言っているとおりです)
この状態で、経済成長が毎年10%にV字回復すると思います?無理でしょう。「古い価値観」では、経済成長を目指すことが当たり前でしたが「新しい価値観」では「脱成長」が既に当たり前になっています。さらに解決すべき問題が少なくなり、仮にあったとしても、解決に必要なコストが大き過ぎてリターンがないためビジネスにならないということも現実になっています。問題がない世の中は経済成長とは無縁です。
僕の見立てでは、向こう10年〜20年は現状維持状態が続くと思います。人々は週5日、朝から夜まで働き、お金を作るために必要ではない仕事をして経済を回すしかないでしょう。しなくてもいいことを一生懸命して、借金を抱えるようなものですが仕方ありません。この10年を新しい社会システムを構築し、GDPではなく幸福度を指標にする移行期間にできれば最高です。
とはいえ、ビジネスの役割は依然として大きいことは事実です。振り返ってみると、我々の生活が豊かになったのは、そこに製品・サービスを提供する企業があったからですよね。これからも、市場にないものを創出することで「新しい価値観」をビジネスを通して広げていくことができるのです。で、やっぱりそこで注目すべきは、人が人として生きるために根本的に必要なもの、食や農業、環境、哲学、文化芸術の分野でしょう。
今までの成功モデルは通用しないし、一本に引かれたレールがないこれからの世界で、「自分としてどう考えて、どう動くか」が重要です。違和感を大切にし、何が大切かを見極める。一つの選択肢や場所にこだわらず、複数の選択肢を持ち、同質の人間同士ではなく多様な種類の人と関わりを持ち、一人ひとりが「自分の軸(芯)」しっかり持って生きくための変容が求められているということです。
個人的には、めちゃくちゃ生き易い世界になってきていることを実感しているし、未来に対してワクワクしかありません。これからの時代が本当に楽しみです。