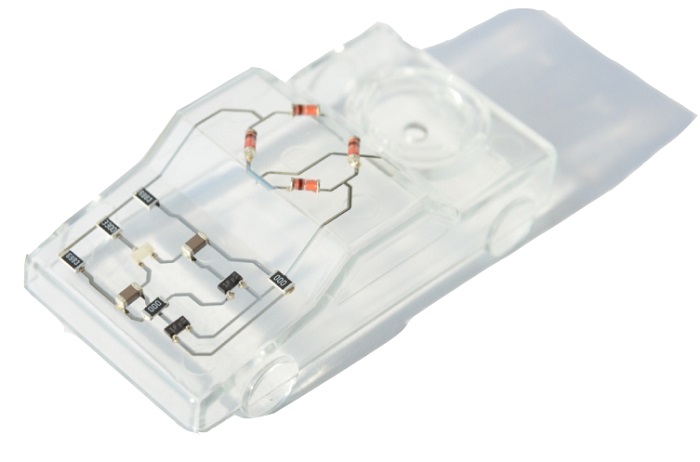・
財布の中に入っている千円、二千円を数えながら日々を生活しているサラリーマン(自分を含む)がInnovationを生み出そうと思っても、それは現実的に難しいという理由の一つとして、「人生、受託仕事」という一言に尽きると思います。お金をゲット出来る手段が、唯一、給料であるからですね。つまり、ニーズあっての仕事だからです。ニーズが顕在化している前提の上で仕事をしても、それはマーケットに対しての「工夫」であって、Innovationでも、Visionでもない。
サラリーマン(=社員)というのは、給料を経営者から得る人達のことです。そして給料とは、自分の労働の対価として会社(経営者)から受け取る物です。つまり、サラリーマンは会社がオーダーする仕事を受託しているのです。会社のオーダーに対して満足の行く仕事をすると、気持ち良く給料を受け取ることができる(オーダー以上のことをした場合は、色が付くかもしれない)。しかし、及第点に至らない場合や、客(経営者)が満足しない場合は、叱責と共に給料も減る。それが、会社と社員の関係です。ちなみに、ここでは経営者が従業員のモチベーションを上げるために取る工夫については言及しません。
しかし面白いことに、ほとんどのすべての会社は、やはり同じように取引先から仕事を「受託」しています。客にサービスや製品を提供し、その対価としてお金を得る。つまり、ニーズが顕在化しているという大前提があって初めて、金をゲットすることが出来るのです。サラリーマンも会社も、マクロ視点では、全く同じ土台の上に成り立っている訳ですね。もちろん、世界のごく一部の企業は「ビジョナリーカンパニー」です。それは、マーケットの期待値やニーズを勘案するのではなく、社会は、未来は、人類はこうあるべき、という概念先行・理念駆動でマーケットを牽引する力を持っている企業です。概念駆動型の企業はリスクを恐れない。だって、マーケットがないから儲かるんでしょ!?という子供のような心を持っていて、実際、そこに全力で進むからですね。最近では、Uberや、Squareがその典型です。
さて、InnovationとVisionに話を戻しましょう。よく「100年続く会社を作りたい」という経営者に出会います。しかし、そんな経営者に限って、「副業禁止」などといった極めてレベルの低いレギュレーションを設けていたり、管理やマネジメントに血眼を注いでいたりするのですが、そんな会社は一代であっという間に終息します。100年続く企業にしたいのなら、Innovationを生む土壌を作るのが先決です。その土壌は何かと言うと、それは「金の心配をしなくても良い」または「金は自分で自由にどんどん稼げ」ということを制度として容認するかどうかなのですね。
前者の場合は、大企業がそれに当たります。大企業というのは、とても素晴らしいオプションを保有しています。家賃補助制度、福利厚生、残業代、社員持ち株制度、ランチ手当、家族手当など、額面に現れない手当で、従業員が千円、二千円を数えながら生活しなくて良いように、ゆとりのある制度と給料体型を数十年に渡って計画的に提供しています。しかし、中小零細企業は、当たり前ですが、そこまで充実した制度を整備する体力がない。よく言われる、「金なし、人なし、時間なし」という典型です(一部、めちゃくちゃ儲かっている中小零細もありますが)。だからこそ、逆に従業員を自由にすべきなのですね。会社としてはこれだけしか出せないけれど、足らない分は、自分で稼いでね。というスタンスでしょうか。
・
少し話が逸れましたが、Innovationを生み出すために中小零細のサラリーマンが出来ることとしては、常に、自分主体で物事を考えることと、これからの時代はこうあるべきという、概念先行で物事を考えれるかどうかです。身近な人間を決して見てはいけない。身近な人間を見ていると、その範囲でしか大きくはならない。ましてや、上司や経営者を見ていてはいけない。そこから先に大きくなる余地はない。企業が経営者の器でしか大きくならないというのは、プランターで育てた野菜が、大きく成長しないのと同じ意味です。だから、自分が大きく成長したいのであれば、会社を見ないようにすべきなのです。
逆に言うと、そういう人間ばかりが集まった集団組織というのは、リミッターが外れた「成長力が青天井な」企業ということが出来ます。そこまで行くと、強い組織ですね。そんな素敵なチームを作ってみたいと思うのが、人の心というものでしょう。
僕は、概念先行、理念駆動という言葉が大好きです。
過去記事でも、色々とその観点から書いています。
理念(理想的概念)とハードウエア、ソフトウエアの関係(2014/3/18)
ソーシャルシティと概念先行型(2013/10/12)
自分の価値、集団として、チームとしての価値を上げるためには、見えないものを見ているかのように果敢に挑戦し続ける力と、リスクを取らない器、100年先に何を残したいのかという、理念とビジョンがあるべきだと思う、今日この頃なのでした。
※この記事は1000%、自省を込めて書いています。
次回は、スクラップ アンド ビルドという資本主義経済の根本について持論を展開したいと思います。(←酔っぱらい)