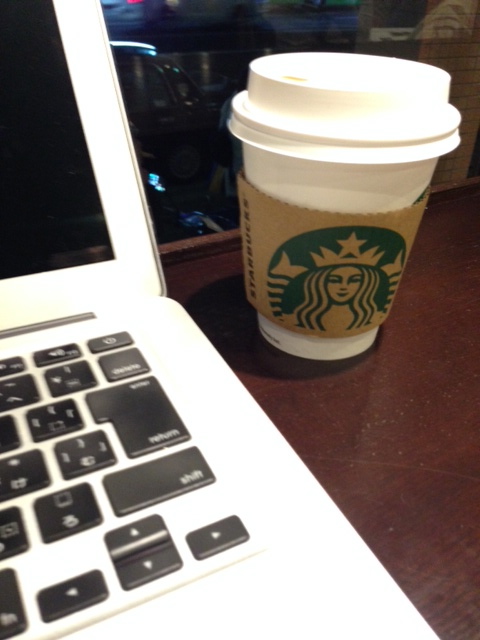・
The capital tribuneに掲載されている記事「ネット経済の行方」を興味深く読みました。
ざっくり言うと、Twitterの利用者数が伸びたものの、閲覧者数が減ったことにより同社の株価が下落したという記事です。Googleのようなインフラ企業はネット人口が増えれば増える程、広告収入が増え、ネットというインフラがある限り安定しますが、SNSのようなクローズドサイトの広告収入は、利用者(会員)数と閲覧数の減少の影響をもろに受けてしまうということですね。FBも同じく、利用者数の伸びは鈍化しているとのこと。
・
ここからはビジネス目線ではなく、あくまでユーザとしての僕の感覚です。
僕自身もTw、FBの利用者ですが、実際、以前に比べて著しくサイト滞在時間は減っています。そう言えば、全体的にタイムラインの流れも緩やかになった(投稿が全体的に減ってきた)ような気もしています。Twでは本ブログの更新情報を飛ばす以外は全くつぶやいていないし、FBの投稿もほとんどがブログの更新情報です。
では、TwitterやFacebookの閲覧回数が減ったからといって、その時間をどのサイトで過ごすようになったのかと聞かれると、答えに窮してしまう。特にどこかのサイトに行っているということもないし、何か別のものにハマっている訳でもない。例えば、通勤時間はアクセスせずに本を読んでいるのかもしれないし、iPhoneのミュージックプレイリストを編集しているのかもしれないし、車窓の景色を眺めているのかもしれない。ただ、減っているのは事実。
そのような「よく分からないけれど、以前と比べてあまり見なくなった」という個人個人の小さい事象の積み重ねが、チリツモ的に大きな数字になっているのかもしれませんね。しかし、面白いのは、この時期になって急に減少のことが騒がれるようになったということです(Twは昨年10月に上場したばかりなのでマーケットはその動きに敏感であるのは当然ですが)。ここに来て、減少が一斉に始まり出したように感じます。FBやTWのように世界中に数億人のユーザを持つメガサイトは、流行り廃りの影響を受けにくいと思っていたのですが(例えばアメリカではすでにピークは過ぎたけれど、日本では大流行している、など)、世界的にこの「小さな何か」を積み重ねた数が、時を同じくして大きくなっているのかもしれません。これはネットのようなボーダーレスかつリアルタイムな世界では当然のことです。同時発生的に何かが起こる。
あるいは、単純に「頭打ち」したのかも。ネットやスマフォが自由に使える国々においては、レイトマジョリティ層まで行き渡ってしまったとか。ちなみにイノベーターからアーリーマジョリティ層までは市場全体の50%くらいと言われていますね。レイトマジョリティまで行けば、全体の84%まで行き渡るという計算です。あくまでマーケの一つの指針ですので参考にしかなりませんが、基本的な考え方としては、スタジアムのウェーブのように一つのスタンドが盛り上がっている時には、既に立ち上がったスタンドは静かに座っているということにもなります。
どんなものでもそうであるように、SNSにも流行り廃りがあります。僕も数年前まではmixi、greeにもいましたが、今では全くアクセスしていません。だからこそ、自分からの情報発信は出来るだけ「個人ブログ」で行うようにしています。閑散とし、自分もアクセスしなくなったサイトに写真アルバムをアップしたままにしていたり、テキストを残していることって、気持ち悪く感じますし、仮にそのサービスを提供している会社がサービスをストップしてしまったら、大切なライフログは(バックアップを取らない限り)なくなってしまう訳ですから。ですから、書きたいことは出来るだけ、自分が管理運営する個人ブログに掲載する。どうしても、そこにこだわってしまいます。
これから、SNSはどのようになって行くのでしょうか。
ネットインフラを利用した個人の情報発信は絶対になくらなないと思いますし、人との繋がりも消えることはないでしょう。TWやFBに代わる新たな形態のサービスが立ち上がるのかもしれないし、SNSに依存しない「個人が運営する個人メディア」が益々増えていくのかもしれない。
いずれにしても、注目すべきニュースですね。