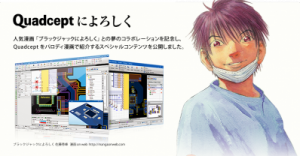・
ここ数年、国内にいても急激に英語を使う機会が増えてきました。大企業や海外でのシェアを持つ会社は今までもそうだったでしょうが、いわゆる「普通の会社」でも国内にいながら、英語を話す機会が急激に増えています。
今やスタートアップス、特にテクノロジー系ベンチャーやITサービス系にとっては英語は必須です。海外に行かなくても、国内でも英語の使用機会が多い。ネットインフラの発達で、WEB-EXやSkype、メールでどこの国の人とも連絡可能。SNSでも繋がることができるし、国内のビジネスイベント、展示会、Pitch大会などでは、半分くらいの人が外国人だったりするのが当たり前。一昔前まではこんなこと、なかったんだけどな。
昨夜、海外メーカーのREPをしている某社長と会食していたのですが、国内から海外へという輸出的な一歩通行でなく、未だ世界第三位の経済大国である日本市場に進出したい海外企業も非常に多いとのこと。そうなると取引の現場では英語は絶対必要ですよね。
・
かくいう当社は海外取引をロードマップのコアに据えているので、今朝はアメリカの大手商社とWEBカンファレンスを行ってレジュメをWEB-EXで共有しながらビデオ会議。こちらは朝9時、先方は米国セントラルタイムで昨夜の18時。時差をうまく使えば、リアルタイムで双方のオフィスにてインタラクティブに会議可能。顔が見えて表情もしっかり分かるから、現地に行かなくても全然違和感なしです。
午後からは、HACK OSAKA 2014がグランフロントのOsaka Innovation HUB で開催されました。ワンセッションを除き、全てのキーノートスピーチ、パネルディスカッションは海外ゲストと日本人が入り混じって全て英語。スタートアップスによるPITCH大会も全て英語です。
当社、Quadcept Inc.もPITCH大会に出場しました。
マーケ担当のYazan Morimotoさん!
今回は知り合いも数社登壇していました。
いつも仲良くさせて頂いている、ビッグデータ、ソーシャル解析のcutting edge、Ontrox社のArita氏。いぶし銀の落ち着いたスピーチ、渋い。
moffさんもがんばっていました!
そんなこんなで大阪にいながら英語一色の一日。なんだか不思議な感覚だ。これ、名付けると「ドメスティック・グローバル」とでも言うのでしょうか。面白い時代です。