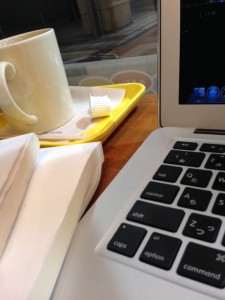・
週の後半はビジネスディナーが続き、更新もままなりませんでした。
季節柄、歓送迎会、配置転換が多いのでこういう機会も増えますが、ビジネスとはいえ人間関係が堅牢な方々との会食は本当に楽しい。学ばさせていただくことも多いし、刺激になります。
・
さて、今週最も衝撃を受けた記事。
NHKクローズアップ現代 〜「“独立”する富裕層 ~アメリカ 深まる社会の分断~」
ジョージア州に、郡から独立したサンディ・スプリング市というのがあるらしい。郡という行政区分から合法的に独立。富裕層が自分たちのためだけに作った行政が「サンディ・スプリング市」。この市の市民の平均年収は1000万円。警察、消防以外の行政業務は民間に委託。人口9万4000人の市の職員は、なんと9人。税収90億円の最も裕福な市は、徹底的に支出を抑え、まさに「富裕層が自分たちの財産を守る」ためだけの市が誕生したとのこと。
一方、市が「独立」したために、フルトン郡の税収は激減。デトロイトよろしく、市のサービス(ゴミ収拾、図書館など)に回る予算がどんどん削減され、サービスの打ち切りが続出。貧困層の生活が大打撃を受けているとのこと。
1%の持てる者と99%の持たざる者の格差。
中間層がいないアメリカの現実ですね。
こうなってくると、「税収」「公共サービス」のあり方、国家のあり方そのものが変わってきます。富裕層がいなくなれば公共サービスは支えられず、行政は破綻。教育、医療サービスを受けることもできず、完全なる格差社会が生まれる。「誰でもがんばれば、夢を実現できる」というアメリカン・ドリームも崩壊し、治安悪化。「北斗の拳」のような荒廃した地域と、セキュリティ万全の地域の「見えないフェンス」で分断された社会が生まれているとのこと。
どこに答えがあるのか
これからの社会はどうなるのか
日本もどんどん格差が広がっています。
教育と医療だけは、全ての人に平等に与えられるべき。
色々と考えさせられますね。
Jazztronik / Butterfly Dance