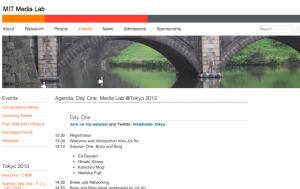・
事情が許すなら、先頭車両に乗りたいのです。
普通の在来線でも十分楽しめるのですが、出来れば、ゆりかもめやポートライナーのような無人の新交通がベスト。目の前にはレールしかなく、あたかも自分が運転しているという感覚に浸ることができるからです。乗車中の能動的体験。もちろん景色も大変に良い。

テクノロジーのカッティングエッジな先生方の話は、まるで電車の先頭車両に乗っている気分を味わえます。先生方の考え方や理論がレールであり、ビジョンをモデル化したものが目の前に広がる景色。
昨日まで東京で行われていた MIT Media Lab @Tokyo 2013 は、まさにこれからの世界はこうなって行く、こうなった時に人はこういう体験をし、このような考え方をするだろう。というビジョナリーばかりが集まるプレゼン、パネルディスカッション。
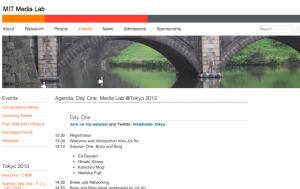
是非視聴したかったのですが、仕事で見れず。こちらにまとめられていたので、ザザッと全文読んでみました。夢中になって時間を忘れますよ。一部、個人的に刺さる箇所のみ、まとめサイトから抜粋してみました。「」内が引用です。それらに対してコメントを追記しています。
「理研の藤井さんによる「SR(代替現実)」。エイリアンヘッド被って見るSR(代替現実)で現実と区別できない世界を実現。」まさにアバターの世界ですね。被験者は迷うとまず自分の手を見て現実を確認するそう。
ここで注目して欲しいのは、人が幽体離脱のような神のような経験をするということ。SRによって人は現実と仮想の区別がつかなくなり、騙されるかもしれないということ。現実と過去が融合する体験。仮想現実の見破り方を議論するとは・・・すごいことです。
「情報も、水と同様に循環し、生態系をつくっている。
例えばhttp://sourcemap.com/ でサプライチェーンを可視化するとそのチェーンが本当にサステイナブルなものかどうか見えてくるということ。」
確かに情報を流水として考えると分かりやすい。soucemapのように情報に色をつけて可視化した時にどのように伝達しているかをトレースできる。プロダクトに関して言うと、理念駆動型であるべきということ。ただ作った、だけでは一時的に消費されて終わってしまいますもんね。
とまあ、ざくっとこんな感じですが、その他、SONY笠原さんによる、カメラ映像に映った物体をタッチ操作すると、実際のモノが動くexTouchや、プロトタイプの作り方、クローズドな考え方はもう古過ぎる、ハードもオープンハード化すべき等の話も必見です。ビシバシ刺激されます。あととにかく登壇されている方の面々が素晴らしい。(実況された林信行さんに感謝です。)
MITの石井先生がおっしゃる通り、「世の中がどう変化して、どこに向かおうとしているかの視座と基軸をもつことこそが大事。」という言葉、心から御意。
個人の価値基準や実体験、成功体験に基づく判断基軸なんていかに小さく稚拙なものか。細かいルールなんてどうでもいい。大きな視点でこれからの時代がどう変化していくかに関する視座と基軸を持つためには情報をどれだけインプットするかだと思うんですよね。フィルターの精度は筋肉と同じで、I/O作業を日々繰り返していれば、徐々に鍛えられて(人や会社から理解されようがされまいが)自分自身の正しい視座を持つことができるようになるんだと思います。普段から違和感を感じていることに対しての自問自答、やっぱりなんだか色々間違っているのかもしれないな、という問い等を含めて、脳内のキャリブレーションになりました。
娘たちも勉強タイム終わったようです。
寒い日曜日ですが、ちょっとクールダウンに出てきます。