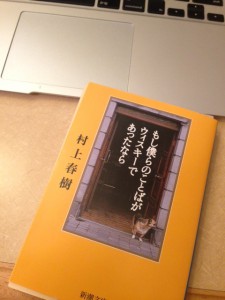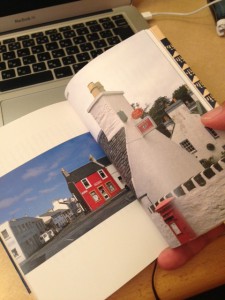・
昨日の記事「新卒入社について一考」の中で、「エリートより、変でもキラリと光る何かがある人間が欲しい」と書きました。
その理由は色々とあるのですが、一つに、自分もいわゆる「一般的なレールに乗った新卒入社」ではなく、家の都合で海外留学を諦め、一度社会に出てから、専門学校と大学に行っているという経歴があります。履歴書(もう書き方も忘れた)は人が見たら「何これ」という言うくらいグチャグチャだったりするので、ある意味マイノリティではありますよね。でも、そのお陰で訳の分からない分野の知識を持っていたり、経験をしていたり、多岐に渡る人脈があったりするので、振り返れば苦労も色々とあったけれど、「常に勉強する」という習慣も身についたし、まあ、それはそれで良かったなとも思っています。
自分のようなケースが良い悪いかはさておき、学生時代から20代にかけて色んな経験を積み重ねるというのは、ないよりかはあった方が良いと思っています。仕事とは直結しなくても、ある分野で深い知識を持つこと、幅広い人脈を作るということは財産になります。特に海外と関わって仕事がしたいという方、僕もそんなに広く知っている訳ではないけれど、少なくとも僕が関わっている範囲の世界では訳の分からない人がたくさんいるので、履歴書なんてあまり関係ないということをお伝えしておきたいです。という訳で学生の皆さんも、「有名企業や一流企業」ばかり目指すのではなく(これが大きなミスマッチを生む)、本当に自分を活かせる、自分を必要とする名も知れない会社がたくさんあるということを覚えていただきたいと思います。そういうところは仕事が激務な上に、人が慢性的に足らなかったりするので、いきなり大きなプロジェクトにアサインされたりして、なかなか面白いですよ。(あ、ちなみに決して新卒入社や大手志向を否定している訳ではなく、仮にそうでなくても大丈夫だよ、ということが言いたいだけです)
もう一つ、日本人は新卒入社が社会の大きなレールとなっているので、社会人になってから専門学校に入ったり、社会人大学院に行ったりする人が多いですよね。ある程度仕事ができるようになると、もっともっと専門知識が必要と感じるようになり、志す人が多いようです。もちろん、年齢を重ねてから初めて必要性に気づくということもあると思いますし、その時は院に行くお金がなかったということもあるかもしれませんが、卒業してからすぐに入社するという結果が、そういう流れを生んでいる一面であるかもしれません。ちなみに、お金も支援もなくてキャバクラでバイトしながら親に頼らず学費を全額捻出し、睡眠時間を削って大学(しかも一流)を卒業したという友人を何人か知っていますが、皆、一様に才色兼備のバリバリのキャリアウーマンです。経験が人を成長させる一例かもしれません。学生時代にありとあらゆることに取り組んで経験を積めれば一番良いのかもしれませんが、まあ、卒業後に何をしたら良いか分からなくても、とりあえず、何かに興味を持てる分野に色々と取り組んでみたら良いのではとも思います。但し、怠けることだけはNGです。
・
「人生勉強」という点について言えば、死生観を否応なしに考えさせる時計が発売されたようです。
寿命まであと何秒? メメント・モリ腕時計「Tikker」(Wired.jpより)
こういう時計を身に着けていると、一分一秒無駄にしないという意識を換気させられるかも。僕も基本的に怠け癖があるので、この時計、発注してしまおうかな。一歩間違えると悪い意味で刹那的になってしまうかもしれませんが、何事も「有限」な方が、人って頑張れる気がします。笑