朝晩は布団なしでは寒くて寝れない高原から帰宅しました。最近は渋滞に縁がなく(ありがたい)、朝7時に八ヶ岳を後にしてすいすいと帰って来ました。関西の猛暑に慣れず、帰宅してからはグッタリでしたが、明日からの仕事に向けて思いを高めています。オリンピックの熱戦にもインスピレーションを受けています。
No Pain, No gain.
よし、やってやる!

二日間のメーカーズの祭典、Maker Faire Tokyo 2016 が閉幕しました。楽しい時間はあっという間。終わると夏休みが終わったみたいで寂しいです。
今年もアツい作品がズラリと並び、会場の熱気も相まって沸騰寸前のビッグサイトとなりました。もちろん、とっても真面目な展示物ばかりなのですが、やはり一筋縄では行かないのがメーカーフェアの醍醐味。関西出身の自分にとっての「褒め言葉」は「アホやなあ」。そういう基準で「オバカ(=最大の褒め言葉)ランキング」を発表したいと思います。全てをくまなく回れた訳ではないですが、目についた作品の中から・・・という限定的な要素もご了承ください。
もうね、見る人が見たら表紙だけで笑死する「マー」(笑)
「ムー」好きの僕も、見事にツボにハメられちゃいました。この雑誌ジェネレータ「マー」ですが、ディープラーニングの技術を使っています。膨大な数のムーの表紙と、古典小説ドラキュラ伯爵をAIに学習させると、どんな画像をシステムにアップするだけで、「ムー」テイストの「マー」を雑誌としてオートジェネレートしてくれます。驚くのは文章もAIが書いているということ。ちゃんと「そのテイスト」になっているんです。すごいんだけど、ほんとオバカさん。ということで、僕の中では文句なしの第一位です。
作者いわく、「コミュ障の自分にとって人と上手にコミュニケーションができる手段を考えた時に、感情表現できるデバイスをいっそのこと頭に被ればいいのではないか。だって、LINEでもメールでも顔文字で感情を表現していますよね。こうなると、表情筋ってもはや要ります?」という作品。「表情筋って要ります?」に爆笑。そりゃいるだろ(笑)でも、真剣に作っちゃうのがメーカーズです。手元のコントローラーで登録されている数種類の表情をディスプレイします。喜怒哀楽を十分表現できるんですから、表情筋いらないよね。ってそんな訳あるかい(笑)
これは作品ではないけれど、とってもオバカさんだったのでランクイン(笑)確かデイリーポータルZのブースの一角だったと思いますが、シンプルでお金が掛かっていないのに、家族連れに大人気でした。そしてアテンドしている女性がめっちゃサバサバしてて真面目なの(笑)ギャップも面白いし、分かりやすい。ほのぼの(笑)
■第四位
UHA味覚糖×千葉工大 キャンディロケットプロジェクト

これこそ超絶真面目、本物のロケットです。ただし、燃料が「ぷっちょ」。信じるか信じないかは別にして、ぷっちょを燃焼させて15kg以上はあるロケットを300m打ち上げるんですから。もちろん落下時は落下傘が開きます。元はプラスチックの燃焼を研究している千葉工大の研究室が「こんな地味なことやってても注目されないから、いっそロケット飛ばそう。燃料もキャンディにしよう」という「モテたい」という動機に突き動かされて始まったプロジェクトだそうです。これはマジでびっくりです。
ホリエモンも出資していることで有名な民間ロケット、インターステラテクノロジズ(IST)。リア充が持っていると身代わりに爆発する幸運のアイテムだそうです(笑) しかも2000円、安くない!!でもね、ロケット開発ってとってもお金掛かるんですよね。噴射される破片を拾い集めて売り、資金にするという熱意と根性に脱帽です。ちなみに、この破片はカーボンです。鉛筆の芯と同じですね。
というわけでいかがでしたでしょうか?
おバカは地球を救う。おバカなことに熱心な人は天才である。そういうコンテキストでいくと、メーカーフェアは地球防衛軍と天才の集まりです。笑)他にも毎度人気のロボットレスリングもすごく面白かったです。今から来年のMFTが楽しみです。
お会いした皆様、話をお聞かせいただいた皆様、そして、すべてのメーカーズ、二日間ありがとうございました!
[ad#ad-2]
昨日の記事の内容と相反するかもしれませんが、実は、7月に入ってからというもの著しく体力と生気が低下していて、毎日毎日錆びついた自転車を無理やりキコキコと漕いでいるかのように、必死で身体をやりくりする日々を過ごしています。
早朝起きて、走って、仕事して・・というのも、かなり無理してやっているところもあります。まあ一度リズムに乗ってしまうとそれなりに気持ちいいし、楽にはなるし、晴れやかな気分になるのですが。元々一日のスケジュールが分刻みで真っ黒になるくらい予定が詰まっていないと気が済まないような性格なので、動いて追い込んでナンボみたいなところがあるのに、ここ最近は気持ちとは裏腹に身体に鞭打たないと動けないということもあり、精神的に参ってしまいます。
ニュースを見るにつけ、親世代、いやそれ以上の高齢の方々が、真夏の炎天下にも関わらず、とっても元気に演説したり、バンザイしたり、泣いたり、言い訳したり、敵を罵ったり、逃げたり、全力で保身したり、深夜まで会議したりして精力的に「生きている」のを見ると、ああ、こうしたイスタブリッシュメントが日本や世界を動かしているんだなと、自分には到底あんなこと出来ないなと思ったりします。信念が人を動かすと言いますが、政治家であれ起業家であれビジネスマンであれ酒場にたむろするオッサンであれ、なんであんなに生命力に満ち溢れているのでしょうか。僕も傍から見ればそう思われているのかもしれませんので、実は元気そうに見える人でも「毎日、命からがら」なのかもしれませんね。
夏バテかもしれないので、急がず焦らず惰性で流されてみようと思います。気持ちの中では時間を忘れるくらい仕事や学びや遊びに没頭できればいいのに!と思うのですが、今は時間を忘れるよりも先に意識が飛んでしまいます(いつ何時、何時間でも寝ることならできます)。今週は金曜から日曜までの東京出張を乗り越えれば、翌週の盆休みは八ヶ岳の山荘に大量の本と共に避暑に行く予定なので、そこまでは何とか生き延びようと思います。
生き延びる。
大袈裟かもしれませんが、結構大事なことです。
20代後半くらいからだと思いますが、悪夢を見てうなされることが良くあります。何かに追われて壁際に追いつめられたり、頭に斧を振り下ろされたり。最後は、
「うわーーー!!!!!」
という断末魔で汗びっしょりで目が覚める・・・という訳です。大体、月に一度、多い時では週に一度くらいのペースで夢の中で追い詰めれられるか殺されます。これは恐らく何か心霊的なものではなく、持って生まれた性質なんだと思います。そう、身長の高い低い、足が長い短いと同じくらいどうしようもないものなんでしょう。つまり、
「楽に行けよ」
「気楽に生きろよ」
「ストレスため過ぎなんじゃねーの?」
とかのアドバイスは一切効果がない類のものです。だって、僕は好きなことをして楽に生きているつもりなんですから!!笑
もちろん、僕だって好き好んで悪夢を見ている訳ではありません。
あんな怖い経験したくないし、起きたら汗ビッショリだし、起きている時間が大体ハードなので寝ている時間くらいゆっくりしたいし・・・それに、なにより家族にすごく迷惑を掛けてしまいます。家人なんか十数年一緒にいるから慣れたもので(実に申し訳ない)、あ、今日は叫ぶなあ・・・というのが分かるらしいのです。というのも、断末魔(?)を上げる前には段階があるそうで、
1, うーんうーんと、うなり始める
2, 寝言を言い出す(例:たすけて〜 やめて〜 など)
3, うなり声が大きくなる
4, 大声で断末魔を雄叫ぶ(クライマックス)
5, 静かになる
こんな具合で、4のクライマックスに向けてちゃんと手順を踏むらしい。
娘達も、1か2の段階で目が覚めて怯えながらママにひっついているらしいのです(怖い思いさせてマジで申し訳ない!)。どういう感じなのか、イラストで説明してみます。
2の段階。うなされ始めます。この時点では、まだ「うーん、うーん」レベルです。
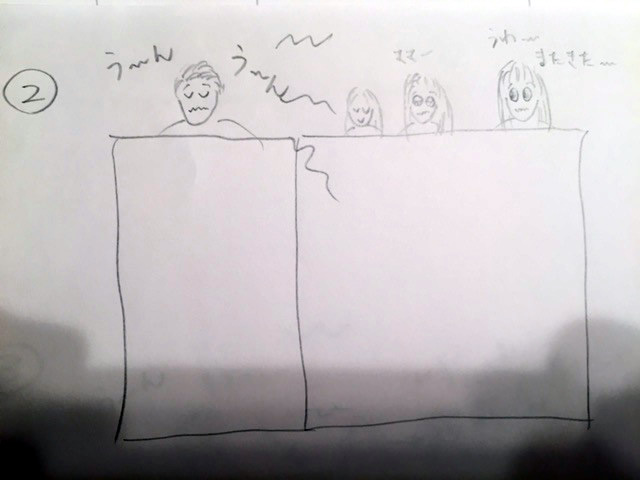
ちなみに昨日の朝は、ほんとに、盛大な
「ゾンビや〜〜!!!!」
で目覚めたそうです。家族に怖い思いさせて申し訳ないですが、なんか自分もとってもかわいそう・・・
なんとかこの夢癖治らないですかねえ・・・性質なので治らないだろうと断っておきながらアドバイスを求めるのも変ですが、せめて周りの人間に迷惑にならないレベルには持って行きたいです。
七夕の季節ですね。
午後からピンポイントで時間が出来たので、ここぞとばかりに走りに出たのですが時間は15時。一日で一番暑い時間に日陰のないロードを走ったものですから身体がビックリして7kmくらいでクラクラしてきました。軽い熱中症のような症状です。無理をせずに近くのコープに駆け込み水分補給しながら涼んでいました。
すると年配の女性が 「あのう・・・」 近づいて来られました。
手には子供の字で願い事が書かれた短冊を数枚持っています。「この短冊、笹の上の方につけてもらえないかしら? お兄さん背が高いから。申し訳ないんですけど・・・」とのことです。もちろんですとも、子供のためなら合点承知の介!!と短冊を一番てっぺんにつけてあげました。普段は無駄に背が高いだけですけど、こういう時に人様のお役に立つことができるんですね。この方、他にも短冊を数枚持っておられましたが、お孫さんのものなのか地元で習字の教室を開いておられる先生なのか・・・とにかく物腰の柔らかいおばあさんでした。手持ちの短冊をすべて付け終わられた後は、デジカメで写真を撮ったりして楽しんでおられました。
短冊には、「パティシエになれますように」、「ピアノがじょうずにひけますように」、などいかにも子供らしい願い事がたくさん書かれています。地元に根ざしたスーパーマーケットは、こういうことがあるからいいですよね。普段どっぷりビジネスに浸かっていると、なかなか地域や地元に目が向くことがないので、とても良い機会になりました。
知的であるかどうかは、五つの態度でわかる。という記事を、Books&apps で見掛けたので、自戒を込めて引用します。
一つ目は、異なる意見に対する態度
知的な人は異なる意見を尊重するが、そうでない人は異なる意見を「自分への攻撃」とみなす二つ目は、自分の知らないことに対する態度
知的な人は、わからないことがあることを喜び、怖れない。また、それについて学ぼうする。そうでない人はわからないことがあることを恥だと思う。その結果、それを隠し学ばない三つ目は、人に物を教えるときの態度
知的な人は、教えるためには自分に「教える力」がなくてはいけない、と思っている。そうでない人は、教えるためには相手に「理解する力」がなくてはいけない、と思っている四つ目は、知識に関する態度
知的な人は、損得抜きに知識を尊重する。そうでない人は、「何のために知識を得るのか」がはっきりしなければ知識を得ようとしない上、役に立たない知識を蔑視する五つ目は、人を批判するときの態度
知的な人は、「相手の持っている知恵を高めるための批判」をする。そうでない人は、「相手の持っている知恵を貶めるための批判」をする。知的である、というのは頭脳が明晰であるかどうか、という話ではなく、自分自身の弱さとどれだけ向き合えるか、という話であり、大変な忍耐と冷静さを必要とするものなのだ、と思う。
分かっちゃいるけど、ついつい出てしまうこともたくさんありそう。実際、心当たりあるし。常に自己チェックですね!
ちなみに、このBooks&appsを書いていらっしゃる安達裕哉さんですが、7月27日の第49回グローバル人事塾に「普通の会社が飛び抜ける 新時代コミュニケーション活用!」というタイトルで登壇してくださいます。場所は東京の麻布。詳細はまもなく人事塾公式サイトと公式Facebookページで告知されると思いますので、要チェック。
今日の写真は快晴のシリコンバレー、El Camino Realです。
記事とは直接関係ありませんが、梅雨を吹き飛ばしたいので掲載しました。ちなみに、僕は今、日本にいます。
それは、サン=テグジュペリの「夜間飛行」にあるようなスリリングな、危険と隣合わせの郵便飛行のイメージではなく、なんとも言えないノスタルジックな、旅情を通り越した郷愁を感じます。
夜という響きと、暗くて静かな機内とは対照的に、月明かりに照らされた雲海、そして数時間後に到着するであろう異国の地に馳せる思いに繋がるのかもしれません。到着後のハードな動きを前にした、しばしの休息。出来るだけのリラックス。僕は大きなスーツケースを抱えてどこに向かおうとしているのだろう。
ジェットストリームというFM番組がありました。
当時遠かった異国の地に対する憧れ、飛行機という非日常。それを彩るかのようなクラシックやラウンジミュージック。それは心地の良い音でした。
最近、Twitterを再開して「銀河鉄道の夜bot」をフォローしました。あのなんとも言えない言葉の数々にハッとさせられます。これもすべて暗闇の中を走る汽車の光景や月明かりに照らされた明るい野原の光景を思い出させます。夕暮れを走る汽車は、千と千尋の神隠しでも出てきます。
「その島の平らないただきに、立派な眼もさめるような、白い十字架がたって、それはもう、凍った北極の雲で鑄たといったらいいか、すきっとした金いろの円光をいただいて、しずかに永久に立っているのでした。」
「僕もうあんな大きな暗の中だってこわくない。きっとみんなのほんとうのさいわいをさがしに行く。どこまでもどこまでも僕たちいっしょに進んで行こう」
「カムパネルラ、僕たちいっしょに行こうねえ」ジョバンニがこう言いながらふりかえって見ましたら、そのいままでカムパネルラのすわっていた席に、もうカムパネルラの形は見えず、ただ黒いびろうどばかりひかっていました。
宮沢賢治の小説には死生観が出ています。死や別れは寂しいものです。旅も楽しさと同時に寂しさもあります。始まりがあれば終わりもあります。ただ時間は流れ、その先を見るのは、信じる心でしかありません。その先にあるものを信じることで、点と点が線として繋がる。
「夜間飛行」という言葉のなんとも言えない複雑な響きは、見えない未来を見る強さと、過ぎ去った過去に対する小さな郷愁から来ているのかもしれません。