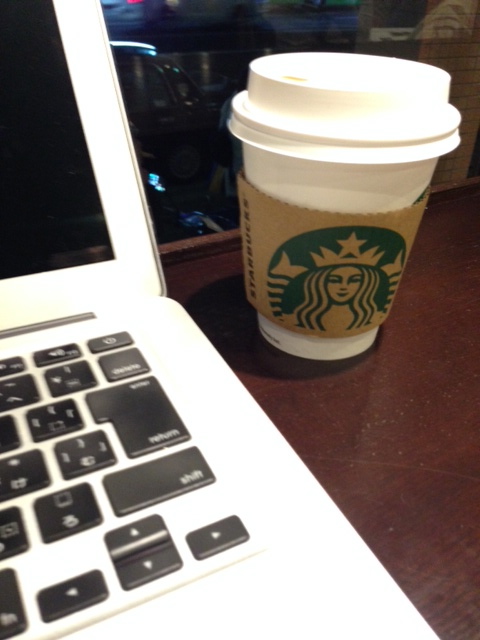・
今週に入ってから、早起き生活をスタートさせています。っていってもまだ三日目。シーズン毎にやってくる「朝型月間」の到来です。暖かくなって布団から出やすくなって来たということもあるのと、後は気分的に。
早起きすることの効果は、先人の「早起きは三文の徳」ということわざにある通り様々な形で実証されていますし、自分も朝が好きということもあって常日頃から意識していることではありますが、なかなか「毎日」という訳にはいかない。特に飲み会が重なるシーズン、寒い冬の季節、習慣的に夜が遅くなるパターンに入る場合などはおろそかになってしまいます。
この冬場、少し早起き生活から遠ざかっていました。復帰のきっかけもなかなかつかめない。そこで、「僕は早起きしますよ宣言」を発動しました。「今週から5:50に起きて、朝の一時間半は仕事と勉強をしますよー」と家で宣言する。そうすると、後には引けない。自分にコミットするための手段です。
でも、意外な副産物もあります。それを聞いていた娘たちが「へー、パパそうなんだ」と興味を示し始める。そんな態度を見て「お?興味ある?僕は6時から勉強することにするけれど、君たちどうする?」というと「わたしたちもー!」となりました。
実はこの反応は想定内。毎朝ギリギリに起きてきて、TVの前でダラダラしている娘たちを見ていて、これは面白くないなと常日頃から思っていたのです。しかし何かを強制させるのは好きではない。自分にはコミットしても、人にはコミットさせたくない。強制は自分のポリシーに反するし、きっと彼女たちも面白くないはず。
そこで「お、興味ある?僕は明日からするけれど、もしかして、一緒にしちゃう?一緒にする人は手を挙げてー」と言うと、「はーい\(^o^)/」となるですね。自分から手を挙げた以上、そこには自己責任が伴うことを彼女たちも理解している様子。「パパは起きるけれど、君たちは起こさないよ。もしするなら自分達で起きて来てね」と念を押します。そうすると、自分達で目覚ましをセットして本当に起きてくる。
こんな感じで、毎朝6時から三人で色々とやっています。僕は僕の勉強をするし、娘たちは娘たちで勉強していて、分からないところがあれば聞いてくる。昨年も一時期こんな感じでやっていたのですが、やっぱり朝型は良いですわ。気持ちいいし、昼も夜もすっきりしたまま過ごせる。そりゃ多少は朝が辛い時もあるけれど、言い出しっぺの責任というか、相乗効果というか、自分だけじゃない「連帯感」に引っ張られるというか。
そんな訳で、ちょっと続けてみたいと思います。
・
今、まさに駅中カフェでPCをカチカチとやっているのですが、BGMはスピード感のあるヘヴィなJAZZを聴いています。何かに没頭したい時はやっぱり indigo jam unit でしょう。
indigo jam unit “Rush” first live take@JZ Brat
)