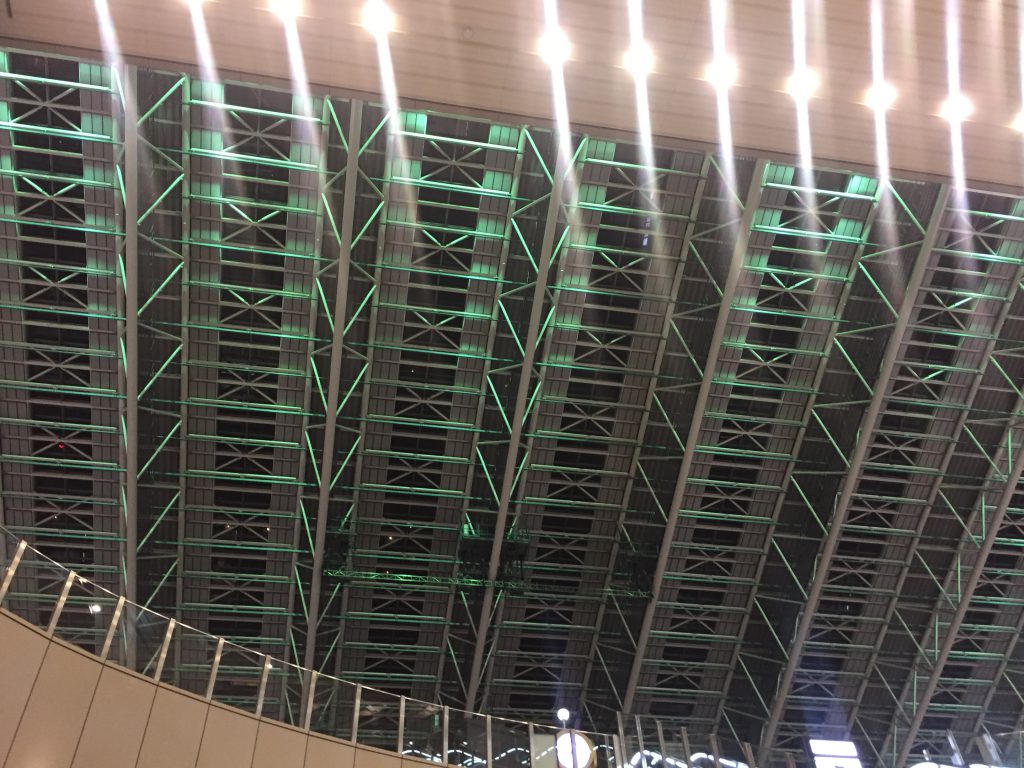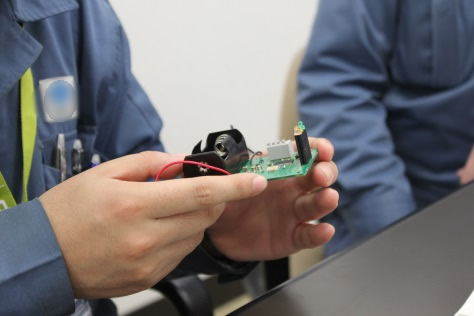最近はもっぱら飛行機での移動ばかりでしたが、今日は珍しく新幹線。東京から最終で帰阪中です。新幹線の楽しみは車内誌「Wedge」を読むことですが、CES明け(といっても二ヶ月経ちますが)ということもあり、話題はAmazon Alexa(音声認識AIエンジン)一色です。今年、Alexaを搭載したワイヤレススピーカー「Amazon Echo」が日本語対応して発売されるかもと言われているからかもしれません。
そういえば今年のCESは、ほとんどの家電がAlexaに対応していて、もはやIntelならぬ「Alexa入ってる」状態。早くも業界のデファクトになってしまいました。対抗しているのは、Google HomeとAlibabaのみ。ここまで来るとどこも追随ができないという点で、ああ、次の10年はAlexa(Amazon)だな、と思ったりします。かつてユーザーとの接点である操作インターフェースは、キーボードから始まり、タッチパネルの進化によってスマートフォンが爆発的に普及しました。で、ここから。これからは声でモノを操作する時代。家電でも、自動車でも、何でも音声で操作です。例えば、台所やリビングなどで需要があるのは「ながら操作」が出来るから。料理をしながら、仕事をしながら。「炊飯器のタイマー、セットしておいて」とか、掃除しながら「トイレットペーパー注文しておいて」とか。帰宅中に車を運転しながら、「寒いからエアコンつけておいて」とか。便利な時代になると共に、生活のマルチタスク化がどんどん進むのではないかと思います。だって、一つ便利になれば、一つ仕事が増えるんですもん。笑
ちなみにAlexaを使っている人に言わせると「ほとんど全ての話掛けに対して人間並に的確に回答してくれる」とのことで、その精度の高さに驚かされるわけですが、Amazonが音声認識エンジンAlexaを開発し、それをオープン化している理由は一つ、世界のeコマースの覇権を握ることに他なりません。だって、みんなAlexaに話し掛けて物を注文しますからね。さらに、Echoなどのスピーカーを家に置いておき、ずっと声で指示を出していると、Alexaさんはとても賢くなります。家族構成、誰が何時に帰ってくるか、いつリビングに人がいるか、日用品の減り具合、週末は絶対にピザか宅配寿司を注文するよね、とか。
つまり、eコマースだけでなく、商品開発などのマーケティングに応用できちゃうし、ホームセキュリティ会社などと協力も出来ちゃうわけです。ホームセキュリティに関して言うと、サンフランシスコのスマートキー、Augustや、昨年訪問したマウンテンビューのnestなどに注目していましたが、今後はどこも(nestはGoogleのグループだからしないかな)Alexa対応が余儀なくされるでしょう。こういうところが、操作インターフェースとOSを握り、ソフト商売をしていくというAIの王道戦略です。そしてアメリカはやっぱりこういうところが強い。
まあ、とにかくこれからはAlexaがかなり来ると思いますが、一方で、ずっとGoogleがそうであるように、全ての個人情報がAmazonに吸い取られて行くわけで(Amazonはついに自宅のリビングにまで入ってきましたね・・・)、逆らえないと思いながらも怖い世の中だなと改めて思います。この時代に対抗するには、自給自足でマインドフルネスを追求したジェダイになるしかないんですから。