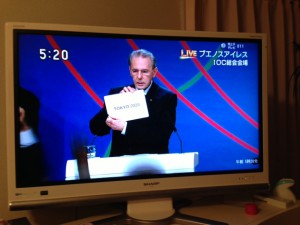・
夕方からの偏頭痛も、関西を襲ったゲリラ豪雨の始まりと共に消え去ってしまいました。やはり気圧のせいかな。後は取引先のレセプションで飲んだビールが血行を促進してよかったのかも。しかし、偏頭痛をお持ちの方は分かると思いますが、あれ、本当に辛いですよね。
なにはともあれ忙しい一日でしたが、無事に終えることが出来そうです。レセプションでの取引先の経営に対する取り組み方もとても勉強になったし・・・良い刺激でした。ありがとうございました。
・
さて、ブロガーサミットが開催されるということで、主催者であり、アルファブロガーとしても有名なAMN徳力さんのブログを見ていて自分もブロガーの端くれとして、その考えに非常に共感する部分もありました。
下記にリンクさせていただきます。
ブロガーサミットで私が表現したいのは、「ブロガー」は特殊な存在ではなく、車を運転する「ドライバー」と同じで、選択してるかしてないかの違いでしかないということ。
専門的なことは是非、徳力さんのブログでお読みください。共感多々です。特にブログのテーマやスタンスは個々に異なるものの、「個人が情報発信出来る時代になった」「個人がメディアになれる時代になった」ということ自体が画期的な事であることは間違いありませんし、僕自身も9年ブログを運営して来てそう実感しています。
個人としては丸8年以上ほぼ毎日更新している経験から、そろそろ僕も「ブロガー」と名乗っても良いのかな、と薄々思うようになってきました。もちろん、「ブログ」や「ブロガー」に対するイメージは人それぞれだと思いますが、まあ、ブログを書いている時点でブロガーである事に代わりはない訳で。つい最近まで抵抗があったのですが、少し考え方を変えてみると、非常に肯定的に捉えることができるようになってきました。
・
さて、個人ブログのあり方について少し書いてみたいと思います。
僕自身は何かの専門に特化しているのかというと、全くそうではありません。仕事柄、マネジメントや仕事に対する取り組み、テクノロジー、マーケ、海外ニュースなどの記事を書くことが多いとしても、仕事の中身そのものはNDA配下にある内容がほとんどですので、なかなかここではご紹介できません。ですから、自分が興味を持った内容に対して、自分なりの(ほとんどの場合、薄っぺらな切り口で)分析や論理を展開していくことが多くなります。もちろん、どこで何を食べた、どこに行った、どこの店が良かった、などの内容も多くなりますが、そういう意味では「読者を意識しない」あくまで私的な内容であり、プライベートなものであるというスタンスです。
では何かを書くというモチベーションはどこにあるのか、あくまで自己満足のためであるか、というと、そうでもなく様々な要因がモチベーションになっています。
例えば、自己との対話であり、情報の整理であり、ライフログであり。娘も二人いますので、いつかパパがこの時こう思ってたんだ、こういう考え方をしていたんだ、と興味を持ってもらえても良いのかな、とも思っています。そして忘れてならないのは、記事の更新を楽しみにしてくれている方の存在です。当然、ブログにはアクセス解析の機能がありますので、どこの誰がいつ見に来ているという個人的な情報は全く取得できませんけれど、一日に何人のユニークユーザーがあって、ページビューはどれくらいで、どのような検索キーワードで来ていて、どんなメディアから流入しているか、というような事は分かります。一日に数百人の方が見に来てくれている、ということは、自分の中では大きなモチベーションになっています(まあ、稚拙な内容ですので、多少の恥ずかしさと申し訳なさはあるものの・・・)。
最初は、何を書こうか随分悩んだものです。ネタを探すのにとても時間がかかったり。しかし、こういう作業を長年繰り返して行くと、真っ白なキャンバスに対する恐怖感がなくなってくる訳です。何も考えずとも真っ白なテキストエリアに、かちゃかちゃとテキストを入力していく。これは恐らく「アウトプットの瞬発力」が鍛えられているからなんだろうと推測しています。毎日毎日、何かを考えることが習慣となっていますから、準備をしていなくても頭の中の引き出しから幾つかのトピックを引っ張りだして、組み立てて、それなりにアウトプットが出来るようになってきました。これは打ち合わせやプレゼンの際に役立っています。
そんな訳で、皆様も是非、何らかのカタチでブログを書くことをお勧めします。デメリットよりもはるかにメリトの方が多いですよ。そしてできれば、SNSに依存しないカタチでブログ(個人メディア)を持つことができれば最高です。SNSは流行り廃れがどうしてもあるので、折角書き溜めたものがなくなる恐れもなきにしもあらず、ですから。
そんな訳で、仮にSNSの滞在時間は減ったとしても、僕はここで日々、何かを発信して行きたいと思っています。
それでは今日はこの辺で。