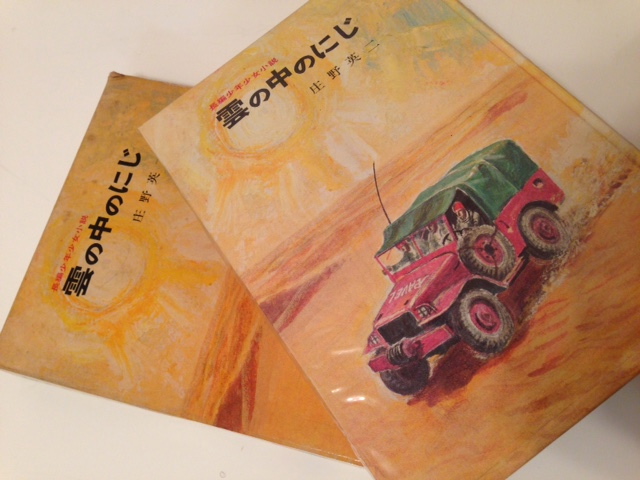・
昨日は今年の初レース「新春武庫川ロードレース」のハーフマラソン。地元の第41回を迎える伝統ある大会だけど初エントリーだった。
僕はほとんどのレースに一人でエントリーしている。当たり前だけど、会場へ向かう電車も、駅から歩いている時も、ゼッケンをウエアに取り付けている時も、トイレに並んでいる時も、ずっと一人。
たくさんのランナー達の中に「自分」という存在が混じっている。これは何かの間違いじゃないのか?と、不思議に思うことがある。日常的に走っているし、レースという一つの目標のために練習しているし、ウエアやシューズも充実させている。レース後にすぐ飲めるように、携帯用の保冷ケースに缶ビールとハイボールも入れて持参している。
それなのに「どうして、自分はここにいるんだろう」と、空中に浮かんで斜め上から一人で立っている自分を見ているような感覚を覚える。不思議でしょう? 一方で、スタート地点に並んでいる時に冷えないように体を動かしながら周りの人を見回し、「ああ、この人達もなるべくしてランナーになった人なんだなあ」と主観的に見ている自分もいる。空中と地上とを行き来しているような、とても不思議な感覚がスタート前の時間だし、走っている時も何故か「自分はなんで走っているんだろう」と思うことが多々ある。
「なるべくしてランナーになる」
これは、村上春樹の「走ることについて語るときに僕の語ること (文春文庫)」の中の一文だ。レース前もレース中も、色んな場面で文中のワンフレーズを思い出す。僕はハルキストでもないし、この本に出会って走り始めた訳でもないのに、どうやら「走ることについて〜」はランナーの心情を本当に良く表現していて、共感する箇所が多過ぎるくらい多く、自分が意識している以上に、ランナーとしての自分に大きな影響を及ぼしている気がする。ちなみに、村上春樹ではこの本と、「もし僕らのことばがウィスキーであったなら (新潮文庫)
」は、自分の趣味とまさに重なるので(もちろん、先生のレベルには足元にも及ばないのだけど)、大好きである。
「マラソンは万人に向いたスポーツではない。小説家が万人に向いた職業ではないのと同じように。僕は誰かに勧められたり、求められたりして小説家になったわけではない(止められこそすれ)。思うところあって勝手に小説家になった。それと同じように、人は誰かに勧められてランナーにはならない。人は基本的には、なるべくしてランナーになるのだ。」(「走ること〜」71P 抜粋)
確かにそのとおりで、僕の周りにいる人たちも、何かがきっかけとなってランナーになり、何らかの事情でレースにエントリーすることになった。そんな人達が2000人集まっている。そして、その人達を応援する人々もボランティアの方々もたくさんいる。なんて素敵なんだろう。だから、僕は仮に自分が一人だったとしてもレースの雰囲気が大好きなのだと思う。そして、シーズンに何回もエントリーしてしまうんだと思う。
・
レースの結果は、まあ合格点。4’47″/kmペースの1:41’23″でゴール(手元では21.21kmだったので、多少誤差はあるかも)。目標の100分切りは出来なかったけれど、本命のレースは4月の芦屋国際ハーフマラソン、そして、フルマラソンの本命は3月の篠山ABCマラソンだ。それらの大会のための足慣らしとしては十分な出来だった。
さあ、篠山まで二ヶ月ない。3時間40分台を目標にしているので、これから一生懸命練習しないと。レース後に美味しいビールを飲むためにも。