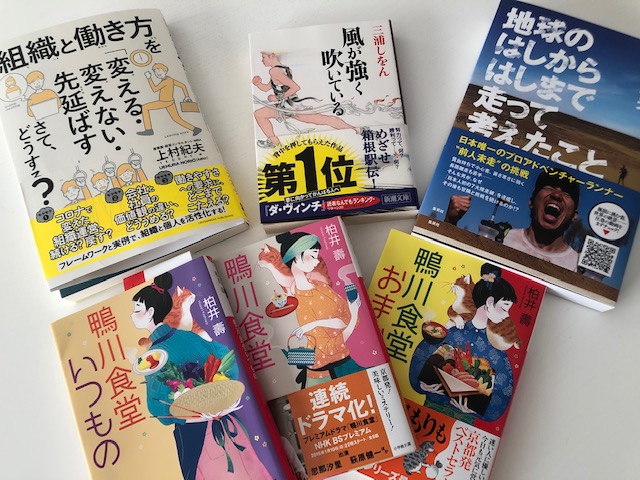一時期落ち着いていたように見えたコロナも、冬が近づくにつれてまた徐々に増えてきたようです。
コロナと経済の両立が言われていますが、一度習慣づいてしまった、オンラインミーティングや、家飲みはなかなか元には戻らないですね。
馴染みの店に聞いても、昼間のランチは良いが、夜の飲み客がなかなか戻ってこない、と。お店にもよるのでしょうが、確かに夜はどこも静かです。これからどうなって行くんでしょう。自分もかつては週に三日、四日は仕事帰りに飲んでいたのに、まあ、もう本当に回数が月に数回、というレベルです。
とはいえ、外飲みの文化は素晴らしい。
僕のような居酒屋や酒場をこよなく愛する人間にとっては、酒場放浪記のような世界がとても好きだし、店の人との会話、客同士の会話や交流から生まれるものがどれだけ楽しく素敵なものか良く知っています。
時代によって変化しなければならないものもたくさんありますが、なくなってほしくない文化もありますよね。