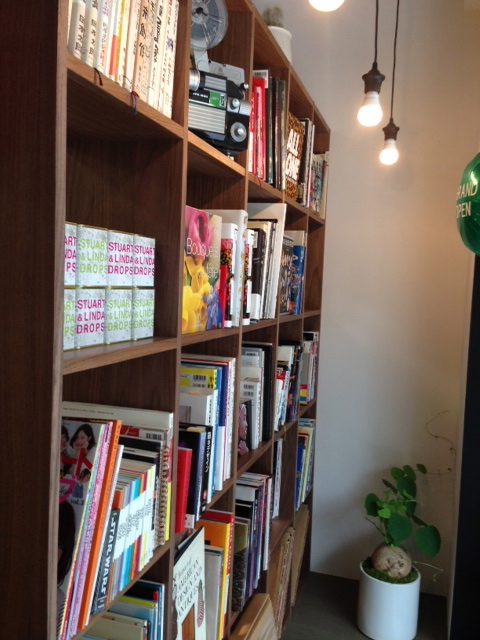・
なんか自己啓発的な、ビジネス書に出てきそうな書き出しですけれど。
ちなみに僕はIT業界に身を置く、しがないビジネスマンではありますが、自己啓発本やビジネス書はあまり読まない方です。本は大好きで(というより活字中毒に近い)常に何冊かはバッグに入れていますが、チョイスにバイアスが掛かっていますのであまり一般的ではないかもしれません。
話が横に逸れました。
仕事のシーンでも、日常シーンでも、「だから何が言いたいのか」を常に考える習慣を身に着けておくと、結構良いことがあるんですよね。一つは考えの整理に繋がること、そしてもう一つは真意を見抜く力が鍛えられるということです。メリット、デメリットの判断、勝つか負けるかの判断、チャンスか否かの判断も瞬時に出来るようになれば、特にビジネス面では相当効率的に事を進めることができますよね。
企画やコンセプトメイキングや提案書などもそう。
削って、そいで、フィルターで濾して、そして最後に残ったもの、それが「まあ、一言で言えば、そういうこと」というコアなロジックです。
今の世の中、あまりにたくさんの情報で溢れているし、営業目線では、言葉を多くしたり、理論武装したり、PowerPointやKeynoteの資料を分厚くしたりすることで、なんとなく「やった感」を出すことがありますが、結局は自己満足です。サイト設計でもそう。あまりにも伝えたいことが多過ぎて、ファーストビューの表示エリアで破綻しているサイトを良く見掛けますが、あれも同じく自己満足。結局、自分達が思っている程、読んでもないし、気にしていないんですよね。発信者が思っている半分、いや、それ以下くらいでしか、掲載している文章を読んでいないのです。ビジュアルも同じ。
であれば、最初から、「言いたいことはこれです。何故かと言うと、こうだからです」と潔く、そしてシンプルに情報を発信した方が、むしろ伝わるし、好感を持ってもらえるというのが僕の考えです。言葉を多くする、話が長い、これらは、単に「周りくどい」という印象だけを残すように思います。
こういうことを書くと、ドライ過ぎてなんだかキツい印象を与えるのでは?と思うかもしれないけれど、言葉には温度があると思っています。心がこもっていれば、人には伝わる。逆に言葉が多くても心がなければ冷たいのですよね。
とはいうものの、このブログでは、身も蓋もないことを実にダラダラと書いていますが、溜まったものを吐き出す場として見て頂ければ幸いです。(←逃げた

それでは、今日はこの辺で。
Acoustic Alchemy – Playing for Time (HQ) by Jazzy Club