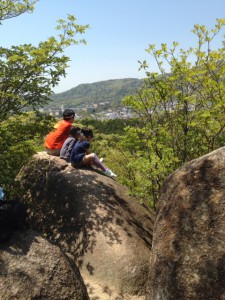・
朝6時から長女の勉強を見るということが習慣化して来ました。
きっかけは、彼女が塾に通うになってから。算数と国語の宿題をたくさん持って帰ってくるのですが、分からなかった問題だけを残しておき、パパに唯一会うことが出来る朝に教えてもらうのです。
僕は教える際、とにかく分からない問題があればその内容を紙に書けと言っています。下手な絵でも何でも良い。例えば、「お父さんとお母さんとA子ちゃんと弟の年齢を足すと、ちょうど100歳になります。お父さんと弟の年齢を足した数とお母さんとA子ちゃんの年齢を足した数は同じです。弟は6年前に生まれ、4年前、弟の年齢の3倍がA子ちゃんの年齢でした」という文章題があるとします。一問目は「弟の今の年齢は何歳ですか」というもの。二問目は「A子ちゃんの今の年齢は何歳ですか」、三問目は「お父さんとお母さんの今の年齢は何歳ですか」。
一問目は分かったとしても、二問目、三問目は小学3年生には少し難しい。文章をさらっと読んだだけでは内容を理解しづらいこともある。でも、文章題というのは、問題の中にヒントがたくさん潜んでいるものです。そこで、自由帳などに絵を描かせる訳です。家族4人の絵を描き、与えられているヒントを書き込んで行く。そうすると、全体像が見えてきます。某◯◯ハイスクールの先生ではないですが「数式ではない、言葉です」という通り、問題の意味と意図をすばやく把握できる子供というのは、頭の中で情景を思い浮かべることが上手な子なんだと思います。絵を描かせるのは、そのための訓練だと思っています。慣れてくれば、そのうち紙に描かずとも頭の中だけで整理しながら読み解くことができるようになるでしょう。
もう一つのポイントは、人に教える事を想定して、自分が学ぶということ。自分は理解出来ている問題を、分からない子にどのように説明するか。こういうことを意識すれば、問題の意図を理解しやすくなると同時に、記憶にも焼き付けやすい。人に何かを教える時、教えている側の方が頭を使いますよね。時として絵を描きながら教えたりもするでしょう。そう意識すると、自然と問題の意図を理解できるようになります。アウトプットを意識したインプット、という訳ですね。
もちろん僕はプロの教育者ではなく、ただの「お父さん」ですから教え方に間違いも色々とあるでしょうが、そういう訳で、今は教えることが僕にとって、とても楽しいことになっています。懐かしさ半分、先生になったような感覚半分。また、娘を見ていると、しっかりしているな、とも思います。僕が小3の時はどうだったか、と考えると朝早起きして勉強なんてしてなかったよな、何も考えていなくて、うんこみたいな子供だったよな、と思うのです。いいオッサンになった今でもあまり変わっていませんが。
・
今日は読み応えのある記事に二本出会いました。
INTERVIEW この10人のイマジネーションが、日本に変革をもたらす:VOL.4_福山太郎【wired.jpより】
育った家庭環境も大きく影響しているとは思いますが、まずやってみよう、と向こう見ずに挑戦するチャレンジ精神、年齢関係なく見習うべきですね。
社員旅行で眺めた日本(NewsWeek 日本語版より)
社員旅行で初めて日本を訪れた中国人4人による座談会です。自分達が中国に対して持っているイメージと彼らから発せられる言葉には大きな隔たりがあるとも感じました。純粋に、そう思ってくれていて嬉しい、という気持ちになります。メディアから入ってくる情報だけでイメージを固定化するのは良くないとも思いましたね。いつでも答えは現場にある。