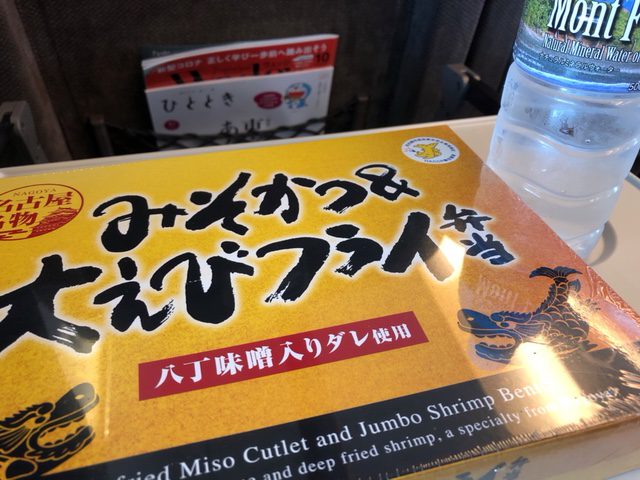皆さんの周りで、どんなことをやらせても確実に結果(=成果)を出す人はいませんか?100人に一人くらいの割合でいますよね、そんな人。どんなことでも出来ちゃう人。こういう人は本質を見抜く力が強い人です。わずかな情報でも、ゴールをちゃんと見据えることができ、そこに向かう最短ルートを走れる人です。
ということで、「確実に結果を出す」ということが今日のポイントです。厳しい言い方をすると、結果が出なければ、そのプロセスは無意味なものになります。
(人によっては厳しい話に聞こえるかもしれませんので、苦手な方はここで離脱してください)
強いていえば、過程による「経験値の獲得」はあるかもしれませんが、まあ、ビジネスの世界での「がんばってます」は評価されません。「やろうと思ってました」は問題外。一度辞めて出直してきた方が良いレベルです。ちなみに、ベンチャーの経営者などで自ら主体的に動き「がんばった」結果が失敗な場合にのみ「失敗は成功の母」という言葉が当てはまります。失敗することによって成功への道が近くなるというのはあるかもしれません。指示命令なく、個人で主体的に動く場合はゴール関係なく、がんばりましょう。ガムシャラやマドルスルー、長時間労働によって身につくスキルや胆力、知識、経験もあります。
でも、組織内においては「結果が出なくても好きなことやれ」と言われているR&D部門や個人でもない限り、結果の出ない仕事は無意味です。
各階層ごとに求められるものも変わりますし、責任の所在地はどこかという議論もありますが、ここではあえて「個」にフォーカスします。
さて、組織内において「がんばった」過程を評価する、これは日本の悪しき習慣である、長時間労働に対する美徳観にも表れます。長時間労働が評価されるのは、工場労働や生産労働など、時間と成果が直結する仕事だけです。仕事のプロセスすべてが財の生産に直結するので、働き手も労働時間に対する対価をしっかり得ることができます。一方、生み出した財が売れない場合は、生産現場は停止し、労働者は自宅勤務になり、報酬を得ることができません。極めてシンプルな構造です。
一方、知的労働の場合の長時間労働は悪でしかありません。
確かに会社に長くいると、一見「がんばっている」ように見えます。でも、ちゃんと休まなければ脳も働かないし、ただ時間を伸ばすだけの仕事は本人の「やってる感」につながるかもしれませんが、知的労働による結果が出なければ、やっている意味がありませんので、これはまったく評価の対象にはならないのです。(あるいは経営者が昭和な人間であれば、その古い価値観で気に入ってもらえるというのはあるかもしれませんが、決算の数字を見て直近3年右肩下がりなのであれば、時代に取り残されて淘汰されつつあるので別の意味で気をつけた方が良さそうです)
「そんなん言われても、めっちゃやることあるんですよ!」という人もいます。では、実際に自分の業務を棚卸ししてみましょう。その仕事の内容は何ですか?書類作成や報告書の作成などであれば、その業務そのものを見直した方が良さそうです。在宅ワークなのにハンコもらいに会社に行くような、至極非効率なことをやっているかもしれません。
それでもタスクに追われて成果が出ない案件が山積みになっているようであれば、手が回らない案件はその人から引き剥がして別の人をアサインするだけです。これはマネジメントの見極めです。単なる能力不足かもしれないので、その人は一旦少ない仕事でがんばってもらう代わりに結果をきちんと出してもらうのもアリです。人による仕事量の濃淡は、報酬差で色をつけます。積み残し案件の精算も、マネジメントの重要な役割です。先送りはビジネスにおいて「機会損失」という致命傷になりかねませんから。
こうなると、一つひとつの時間の使い方も検討しなければなりません。結論の出ない会議や、相談しなくても自分で考えて動けばいいような無駄な報連相、参加者が少ないのに習慣的にやっているだけのセミナーなどは悪です。なぜか?
求められる結果(=ゴール)が収益なのであれば、そのゴールに結びつかないからです。会社にとってはそこにアサインしている人間の給与を支払うわけですから、時間とコストの無駄でしかないのです。
大切なのは、自分の仕事にしっかりとゴールという旗を立てること。ほとんどの場合、ゴール(=成果)は数という単位で計られます。このゴールという旗を立てれない、あるいは見えてない人のなんと多いことか!
でも人間完璧ではありませんからね。未達なことも計画的にやれないことも、コロナ禍のような予期せぬことも起こるわけです。これは仕方ない。その場合は旗を立てる場所を変えるか、やり方を変えましょう。このブログで何度も言っていますが、今、時代は過渡期です。柔軟に変われる人とそうでない人で大きな差が開きますよ。
いずれもしても、常にゴールを見据えて走る。いつまでにゴールするか期限も決める。そうすることにより、効率的に動き結果として余った時間は、学びに当ててもいいし、人に会う時間にしてもいいし、リフレッシュに当ててもいい。そうすることにより、また仕事のパフォーマンスが上がります。
とにかく、今はいろんな意味で正念場ですよね。
個々の力のレベルアップが求められています。古い価値観を亡霊のように身に纏っていれば、いずれ沈みます。環境を言い訳にしていれば、リストラの対象になります。
自分の人生は自分のものです。
仕事の出来る人間=成果を出す人間になるために、ここはひとつ、がんばって行きましょう。