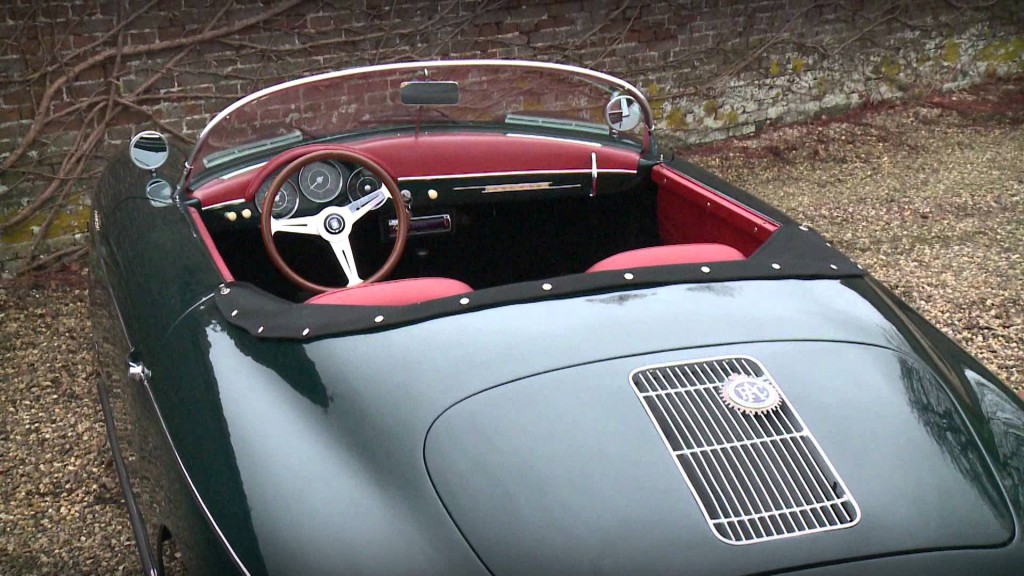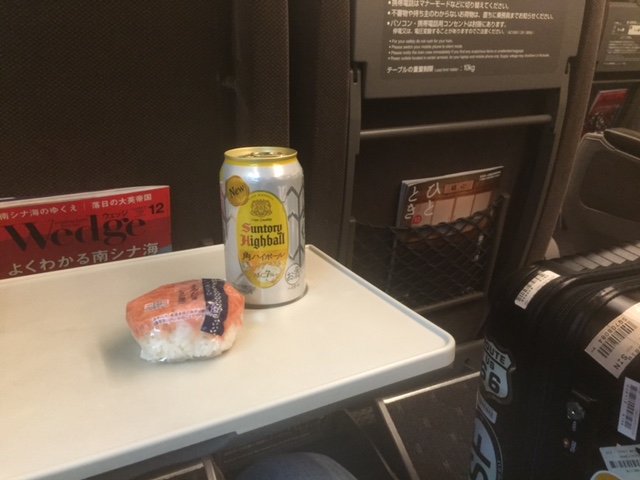友人NさんがシェアしていたデイリーポータルZの記事がとても良く、今日はその真実を探るべくジョギングをしてきました。というのも、その記事はかつて防波堤だったところがそのまま道路になっていることを、千葉の浦安と兵庫の芦屋で検証している記事で、芦屋の防波堤跡は僕は日々走っているとても身近な場所だったからです。
浦安と芦屋の海を失った防波堤(デイリーポータルZ)
芦屋で臨港線と呼ばれている道路沿いのコンクリートのこの壁が約50年前まで海と陸を隔てていた防波堤です。
赤が自転車優先、緑が歩行者優先で色分けされていますが、下の写真の向かって左側はかつて海だったところ(埋立地)になります。写真に写っているのは兵庫県立国際高校という授業を英語で行う帰国子女が半数を占める高校です。そのさらに海側にはシーサイドタウンがあり、今では運河を挟んでさらに南側にも広大な埋立地が広がっています。この防波堤も随分内陸に位置するようになってきました。
右側はかつて防波堤に守られていた宅地です。明らかに埋立地側よりも海抜が低いですよね。いつも走っているところなのにあまり意識したことはありませんでした。改めて見ると、この作りは明らかに防波堤ですよね。芦屋浜は1969年から埋め立て事業が始まりましたので、今から46年前、ここから先は海だったということが分かります。
かつての防波堤に向かう傾斜です。
記事によると、防波堤は相当に頑丈な作りになっていて、破壊するのが大変だそう。それに別に破壊しなくても埋め立ててしまえば、土台としてはしっかりするので良いような気がします。
ここはかつて水門だったんですよね・・・感慨深いです。
芦屋浜はかつて、松林が美しい砂浜でした。
今でも芦屋川沿いの公園にその名残を見ることができます。今日は1月17日。震災で亡くなった方の慰霊祭が行われていました。走ったのは夕方なのにまだ記帳に訪れている人がいました。こういう光景を見る時に命について考えさせられます。
人間のすごさは、一人一人は小さいにも関わらず海を埋め立て、建造物を作ることです。それはまるで大きな蟻塚を作る蟻のようでもあります。僕が巨大建造物に惹かれるのは、そういった点からかもしれません。