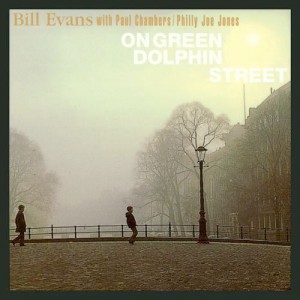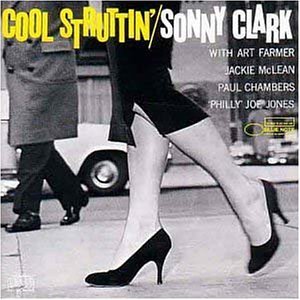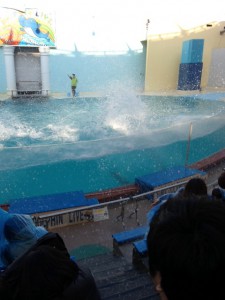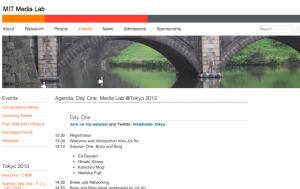・
打ち合わせ終わりで駅に向かっていると、小学生の女の子二人が後ろから追い抜いて行った。
一人は自転車、一人は走って。
ああ、走ってる子は何かの事情で自転車がないんだな・・・でも、いじらしくて偉いな、と見ていると、その子が曲がり角の縁石につまづいて派手にこけてしまった。両膝を擦りむいて痛そうにうずくまっている。自転車の子はそれを心配そうに見ている。思わず立ち止り、所持していたバントエイド三枚を「大丈夫?これ使いなー」と渡したが、あとから考えると、イマドキの子は知らないおじさんから声掛けられたら無視しなさい、などと教えられてるのかな、と複雑な気持ちになってしまった。そして、なぜかそう考えた自分に違和感を持ってしまった。なぜだろう、当たり前のことを普通にしただけなのに。
彼女達も二人だから安心したのだろう、恥ずかしそうに黙って受け取ってくれたが、これが一人だったらどうだっただろう。僕は声を掛けただろうか。そして、彼女はバンドエイドを受け取ったのだろうか。普通の世の中で、普通の感覚を持っている人間なら反射的にそうするはずだ。手持ちのバンドエイドがなかったとしても、声くらいは掛けるはず。うん、大丈夫。僕は「二人の娘を持つ父親」じゃなかったとしても、きっとそうしたはずだ。
我が娘たちのことも重ねて考えてみると、こういう場合には警戒すべきは警戒しつつ、それでいて人の親切や温もりはしっかり感じて心は貧しくならないでほしいと願う。自分もそうだったし、娘たちもそうだけれど、子どもにとっては怪我した時のバントエイドは魔法の薬になることを知っている大人がたくさんいるのだ。でも一方で、「どこからどこまでが親切で、どこからがそうでないのか」、それを子供に判断させるのは本当に難しいと思う。どうしてこんな単純ではなく、複雑な世の中になってしまったのだろう。
思い返せば自分も子供の頃は近所の人たちに色々と助けてもらった。小学校一年生の時、下校途中にShit my pantsしてしまい、ポロポロ泣きながら立ちすくんでいると道を掃除していたおばさんが「どないしたん、大丈夫!?」と声を掛けてくれ、自分の家に連れて行き風呂場で洗ってその家のお兄ちゃんのパンツを貸してくれて家に送り届けてくれた。今から考えるとなんて親切な人だったんだろうと思う。会えばお茶や煎餅をくれたおばちゃんもいたし、怖い爺ちゃんもいた。
・
人と人との繋がりが希薄になっている世の中だからこそ、地域コミュニティの大切さを実感する。子供たちは地域で育てるということに同意するし共感する。そりゃ、確かに変な人はたくさんいるし、痛ましい事件もたくさん起きているのも事実。決して許されることではないし、何かあってからでは遅いので、僕も娘たちには注意するよう良く言って聞かせている。親として子供は何があっても守らなければならないし、子供たちにとっても自分の身は自分で守らなければならないのは明白な事実。
でもね、例えば、阪神大震災の時ってどうだったか。知らない人でも皆が声を掛けあって無事を確かめ合い、励まし合った。東日本大地震の時もそうだったはず。特にこのエピソードは何度も読んだ(大槌未来新聞「流された人が笑顔で手を振っていた「ニコーっと笑って、お前もか、って」)。
ややこしい世の中になってしまったと嘆き、人に手を差し伸べないで無関心を装うこともできるけれど、やはり、僕は正しいことは正しいこととして躊躇せずに行なっていこうと思う。大きなことは出来ないけれど、そういう気持ち、取り組みの一つ一つが良い社会、強い社会を作って行くことに繋がっていくと思う。
そんな事を考えた、3.11。