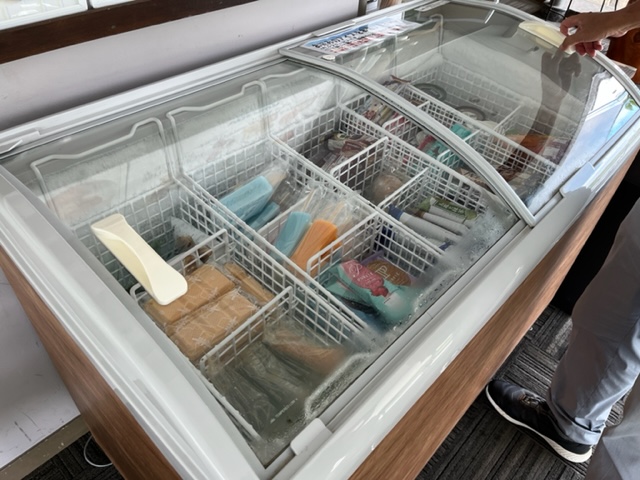乗ったり撮ったり時刻表を研究したりはしないのですが、鉄道の単線が大好きでして。
地元の阪急甲陽園線が、夙川駅から甲陽園駅までの単線というのもあるかもしれません。子供の頃から見慣れた風景にはいつも単線があり、それが理由なのかどうか分かりませんが、単線を見ると異様に気分が上がり、自然と笑みがこぼれてしまいます。(ちなみに、阪急梅田駅や南海なんば駅のようなターミナル駅も好きです。)
先週と今週、たまたまなのですが二週連続で単線に乗るという経験をしました。
先週は東急世田谷線。会食に呼んでいただいた場所が世田谷駅で、滞在しているホテルからのルートを見ると、田園都市線で三軒茶屋まで行き、そこで世田谷線に乗り換えろと指示が出ています。田園都市線はいつも乗っているおなじみの路線ですが、世田谷線は初めての乗車です。もちろん三軒茶屋駅に着くまでここが単線とは知りませんでした。
もうね、改札入ってびっくりですよ。
世田谷線の三軒茶屋駅がターミナルであることで喜び二倍増しです。しかも区間一律料金で、乗る前にバスのようにピッてやるんですね。一般道を横断する時は信号待ちまでするし、ちょっとした路面電車感もあり、素敵すぎます。

そして今週。
日曜日がオフだったので、鎌倉まで足を伸ばしました。鎌倉は好きな街で、海山が近いのも地元阪神間を彷彿とさせるので関東滞在中に海が恋しくなれば鎌倉に行くという感じです。
単線といえば、みんな大好き江ノ電ですよね。
狭い住宅街を縫うように走る江ノ電、最高です。

なぜ魅力的なのか。
電車と人や住宅の距離が近いから良いのかな。自分でも良く分かりませんが、長期出張の良い思い出になったことは確かです。
もちろん、鎌倉ひとり街歩きも良かったですよ。前回来た時には新しいお店ができていたりして。お盆休み真っ最中だからかな、観光客も海水浴客も結構おられました。
夏ですね。