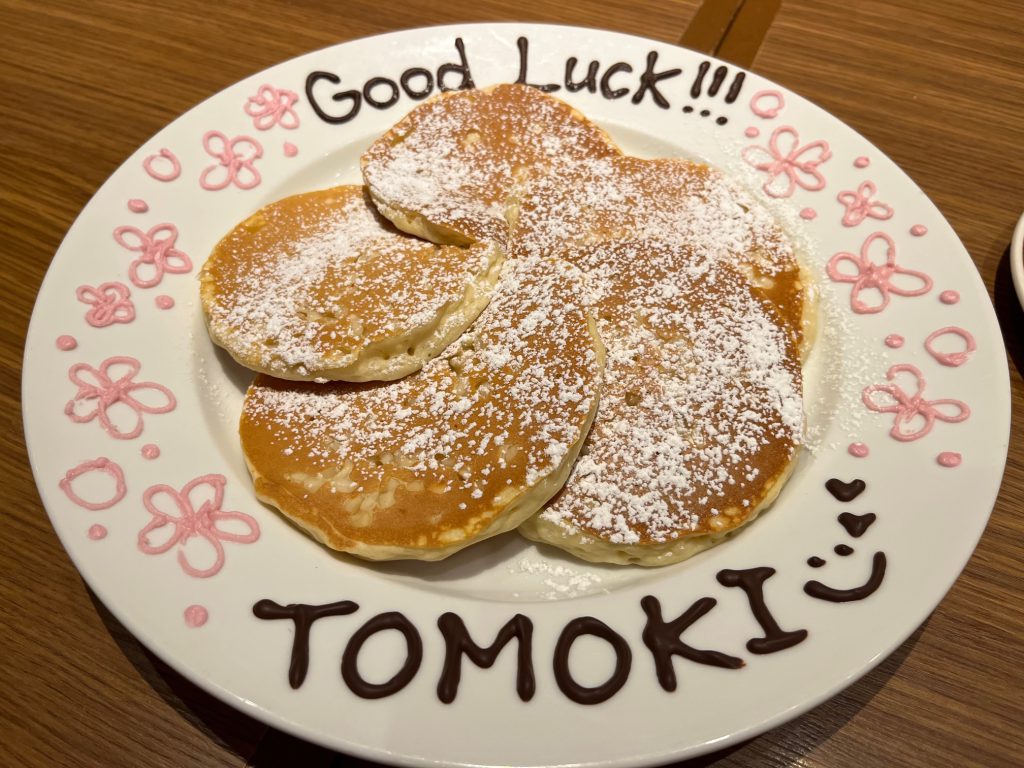世の中もっとシンプルで良いのではないのかなと思う時があります。
カオス理論のバタフライ効果ではないですが、ブラジルの1匹の蝶の羽ばたきがテキサスで竜巻を引き起こすかの如く、世の中は複雑にシステムが絡み合っていて、何かの偶発的現象が別のどこかで不具合を引き起こすようなことが毎日のように起きています。
オミクロン株のまん延と、マクドナルドのポテト不足が関係しているのも同じですよね。一見、まったく関係のない二つの要素がリンクする。株価もそう。インフレ懸念のテーパリングは理解できたとしても、なぜこれほど株価が不安定なのかここまで社会の仕組みが複雑になってくると、将来どうなるかの予想なんて専門家でも難しいのではないでしょうか。
マクロからミクロに視点を移しても同じで、例えば組織運営も、売上予測も、人流も、目先は見えても3年先なんて分からないもの。世の中、ある一つの出来事でガラリと変わってしまいますからね。そこで必要なのは賢い頭や理論ではなく、変化に柔軟に対応できるかどうか、あるいはピボット力ともいうべき方針転換力だと思っています。
冒頭の「世の中もっとシンプルで良い」という話題に戻すと、最近Youtubeで、うどん屋、そば屋、寿司屋などの厨房に密着し、仕込みから提供までを見せてくれるチャンネルにハマっていまして。すごく学ばされるのです。
特におすすめは、「うどんそば 大阪奈良」や「鮨、寿司専門」などのチャンネル。職人さんたちの長年の経験と技術による一切の無駄がない洗練された動き、素材に対する愛、お客さんに対する対応、厨房での笑顔、これらを見ていると、ただ「旨いものを提供する」というシンプルな目的に対して持てる武器すべてを集中させるというプロ意識に感服します。
老舗の店では雇用者と従業員が家族のような関係で、高齢の板前さんと腰の曲がった女将さんと一緒に、若いベトナム人の出稼ぎの女の子が屈託のない笑顔をお客さんを見送る様子などを見ていると、そうそう、仕事って本来こうだよなと思って、胸が熱くなるのです。
自分はとにかく「カオス」をどうにか紐解き、理解しようと思っていたのかも。土台無理な話なのに。世の中はもっとシンプルでいい。なんでも効率化とかKPIとかKGIとか、結局そんなの、コンサルタントの飯の種でしかないんだよなあ(怒られるやつ)。だって、本当に社会課題を解決するソリューションがあれば少子高齢化も解決できるし、税金、物価、社会保険料は毎年上がれど、30年間も可処分所得が増えないなんてことになってないでしょう。働くだけ貧しくなってしまうという、おかしなシステムなんですよね。ちなみに、今年から来年にかけてはもう一段厳しくなると思います。グローバル化って色々と日本には合ってないんでしょうね。
日本はもっと日本らしいやり方がある、と、特に和食の個人店の厨房を映像で見ていて実感します。良いものを安く仕入れ、それを技術で美味しくし、適正な価格で提供する。それが顧客を満たせば、またリピートしてくれるから商売はうまくいく。
今一度、シンプルに物事を考えるトレーニングをしてみたいと思います。