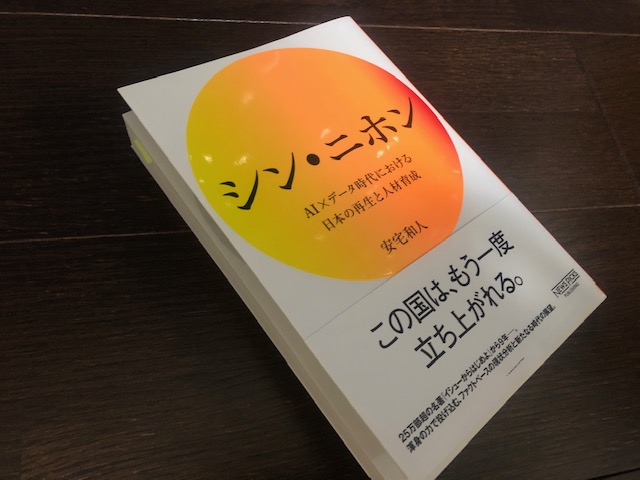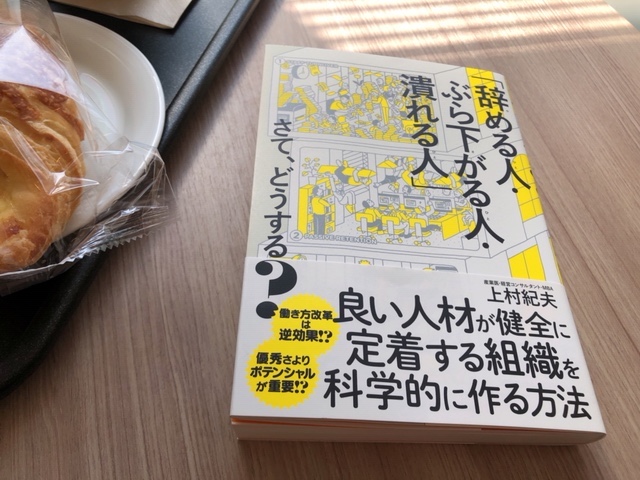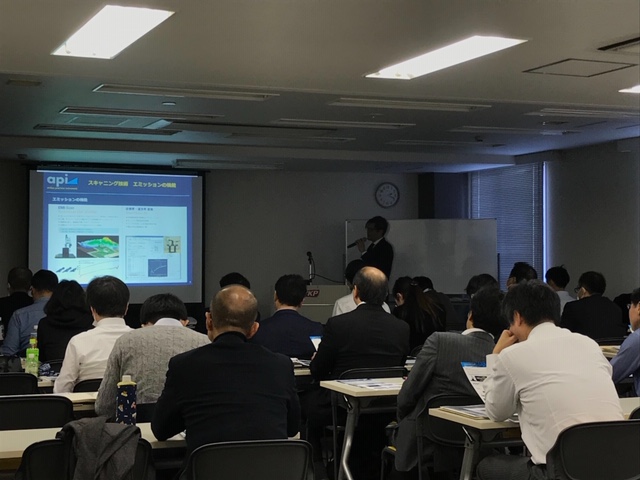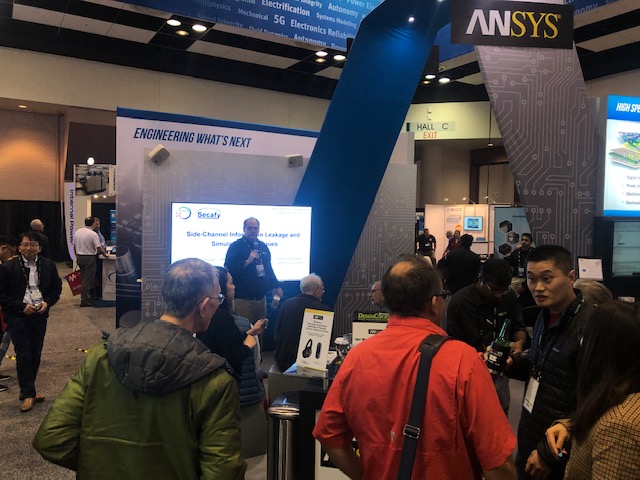FBでもシェアしたのですが、植松努さんのブログに「成長を止めるもの」という記事があり、その内容が今の自分にピッタリ当てはまる内容でした。そして、これはおそらく、潮目が変わる時代の只中に生きるすべての人にも響く内容なのではないのかと思います。
つまり、「変化に対応できない人は、そのまま退場しなければならない」ということなのです。詳しくはリンク先をご覧ください
いま、日本は大きな価値感の変化にさらされています。
企業も、教育もです。
でも、今までやってきたことや、信じてきたことが通用しなくなったことに、絶望する必要はありません。怒る必要もありません。新しい価値感を否定する必要もありません。
すべきことは、新しい時代に対応する事です。
植松務さんのブログ「成長を止めるもの」より
「今までやってきたこと、信じてきたことが通用しなくなる」。
これ、今の時代の大きな特徴です。急に、いや、急ではなくても、徐々に「おかしいな、結果出ないな、このやり方でうまく行ったのにな」感じるようになるのです。それを薄々感じてきた時に、まだ今までの成功体験にしがみつくか、思い切って舵を切り替えるかで、未来は大きく変わります。
実は、この「思い切り」ってとても大切です。
今までのやり方でも通用する部分が100あるとして、それが20%づつ通用しなくなったとしても、まだ1年後は80、2年後は60と、0にはなりません。0にならないから、まだそのやり方で通用する人たちがいると思って、そこにすがってしまうのです。
でも、それは延命、時間稼ぎにしか過ぎず、決してプラス成長にはならないのです。多くの経営者は「変える」ことが「過去、成功してきた自分に対する否定」と感じることが多く、結果としてしがみついてしまい、時代から取り残されてしまうのです。すぐに会社は潰れなくても、その場その場でやりくりすることに必死になり、新しいことに対する投資なんて夢のまた夢、そうこうしている内に「変化に柔軟な企業」がどんどん追い越して行って、いずれは退場、ということになるのです。
良くこういう話をする時に、「大企業はまさにそれ、ダメだ」なんていう人がいますが、とんでもない。逆です。大企業はとにかく実・量ともに圧倒的に強い。確かにダメ企業もあるかもしれないけれど、僕が知る限り、大企業にいる人は、(基礎学力含め)とても優秀な人が多く、20代、30代の若手社員が、個人で自発的に部署横断でワーキンググループを作って勉強会を開いていたり、次の世代を作って行こうという意識がすごく高い人が多い。個人のポテンシャルが元々高いのは、学士でも修士でも英語で技術論文ちゃんと読んでたりするので、大体みんな英語なんて普通に出来たりする人が多いことに現れていますよね。さらに会社として使える金が多いので、研究開発費に潤沢に投資ができる。
一番の問題は、日本の企業数の90%を占める中小零細です。
中小零細は、オーナー経営者が一代で作り上げた会社が多いので、それこそ「過去の成功体験」から脱却することが、様々な属性の人が山のようにいる大企業よりも難しい。それに、使えると金と人が著しく少ないし、ポテンシャルも劣る。で、そこを補うために「なにくそ根性の精神論」とか「想いの強さ」とかに行くんだけど、違うんですよ。
答えは一つで、生き残るためには、「頭を使うこと」なんです。
ノムさんが亡くなられて、今週末も色々と追悼番組が多く放映されていました。一つひとつの言葉にとても重みを感じます。南海、ヤクルト、阪神、楽天・・・弱いチームができることは、ただひとつ、頭を使うこと。創意工夫。それだけなんです。
さて、今日のタイトル「変化に柔軟に対応するって、具体的にどうすればいいの?」に対する答えなのですが、僕は以下をすることだと思っています。
・前年比マイナスなら、前年と同じことを今年はしない。
・赤字が3年続けば、潔く負けを認めて、やり方を捨てる
・競合の情報を常に収集する
・業界における自社の立ち位置を正確に知る
・研究開発に投資する
自戒をこめて。
昨年書いたブログの中でも人気だったこの記事も参考までに張っておきます。今読んでも、いいこと書いてるわ(笑)
「小さい世界で徒党を組んで傷を舐めあってる人間がとても残念な理由について(毒注意)」