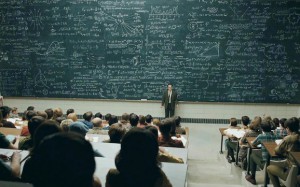[ad#ad-2]
どうも、「腰」や「痛」を連呼するブログにようこそ。
僕は相変わらず四つん這いに近い状態で元気に生きております。
ここ数日、仕事のメールやプライベートの連絡、FBなどで、「ブログを見ましたが・・・」とお気遣いのお言葉をたくさん頂戴しており感激しております。稚拙なブログなのに意外とたくさんの方に見ていただいているんだという嬉しさと恥ずかしさで胸がいっぱいです。心のこもったお気遣い、お見舞いの言葉、本当にありがとうございます。
驚いているのは、「実は私も腰が・・・」とか「頚椎を・・・」とか「膝関節を・・・」という方の多さ!皆様、関節や神経の痛みを良く御存知だからこそ共感していただけるようで、なんだか強い「痛みの連帯感」(結束力?)のようなものが生まれ、自分以外にも仲間がたくさんいるんだと思うと、本当に心強く思います。しかし、これほどまでに皆を苦しめる痛み、いっそ人間は脊椎や関節のない軟体生物だった方が良かったのではないかとすら思いますよね。
・
さて、ようやく少しばかり動けるようになったので、昨日病院で診察を受けてきました。普段は腰痛で病院なんて・・・と思ってしまうタイプなのですが、ちょうど幼馴染の同級生が近くの病院で整形外科医として勤務しており、一度ちゃんと診てもらおうと思ったことも背中を後押ししたのです。割と規模の大きな病院で、設備も良くスタッフさんも親切な方ばかり。正月明けということもあって患者さんでロビーや待合は混んでいましたが、すぐに診てもらい、まずはレントゲン。骨には異常なし、ということだったのですが、もしかして椎間板かもしれないということでMRIの検査へ。人生初MRIです。噂に聞くほどの不快感はなく、気づくと眠ってしまっていました。検査が終わり、また診察へ。ちなみに短い待ち時間でも、やはり激痛でジョジョの奇妙な座り方になってしまっています。あれだけはどうしようもない。
診察室へ呼ばれると、同級生のかー君先生がいつもの優しい顔でモニターを見つめています。「これ、見てみ。ここが骨ね、で、この骨と骨の間が椎間板。これが脊髄で、この中にほら、神経がたくさん通ってるよね。この2番目と3番目、4番目と5番目の骨の間の椎間板がごっつい出て脊髄を圧迫してるよね。特に2番目と3番目が・・・うわー、大きいね。これ、ヘルニアね。椎間板ヘルニアやね。」
「ヘルニアね。椎間板ヘルニアやね。」
・・・出た、あの噂に聞く「ヘルニア」。
まさか自分が・・・という思いで、目の前に映し出される己の腰の画像、3Dの画像に釘付けになりました。鮮明に映し出される画像、かー君先生の丁寧な説明。誰の目にも明らかなほど大きなヘルニアです。認めざるを得ない訳です(当たり前)。自分の身近な周りにも椎間板ヘルニアや頚椎ヘルニアの人がたくさんいます。そして皆の苦労も良く知っています。ああ、これからずっとこの病と付き合って行かなくてはならないのか・・・と思うと、一瞬目の前が真っ暗になりました。なぜか今まで「自分はただの腰痛持ち。ヘルニアなんて大袈裟なものな訳がない」と高をくくっていたのですが、まあ、なって当然かなという思いもあります。バスケ、スキー、ゴルフ、マラソン。長時間のデスクワーク、身長が高いので姿勢が悪くなってしまい、腰に負担がかかっていたこともあるかもしれません。そして数年悩まされている慢性的な腰の痛み。ただの腰痛持ちでは片付けられない痛みの原因がはっきり分かったので、気持ちがスッキリしました。
「えっと、とりあえず、スポーツは3ヶ月厳禁ね。
ゴルフ、マラソンだめよ。」
はい、了解です。長い人生、多少ブランクがあっても無問題。
かー君先生いわく、ヘルニアは一生ものでもなく、画像では残っていても鎮痛剤なしで痛みが消えることも良くあり、スポーツも復帰できることも良くあるので、あまり心配しないことだ、と言われたので、まずは無理せず安静にしておきます。4月の芦屋ハーフマラソンは父や娘達も楽しみにしているので、食材持って応援団として参加しようかな、なんて考えています。多分、今年一年はマラソン休業。一緒に走ろう〜って言ってた皆様、ボランティアや応援団で参加しますのでね!暖かくなれば、マラソンの代わりにトレッキングポールを使ってハイキングも楽しめますしね。ゴルフの方はインターバル後、ボチボチ出来そうです。関係各位、ゴルフコンペはGW前にしてください。(自分勝手w)
という訳で、ヘルニアクラスタの皆様、新米ですがどうぞよろしくお願いします。しかしあれですね。人間って歳を取る生き物なんですね。今まで健康そのものだったのが、ここ2〜3年の間に出るわ出るわ、病気のオンパレード。37歳目前にしてまた一つ追加されました。今まで肉体と精神を酷使してきたツケと言えばそれまでなんでしょうが、みんな同じと言えば同じです。仕事で知り合う方々も、大きな声で言わないけれど大体何か持ってらっしゃる方がほとんど。うちの会社にもゴロゴロいます。病気や障害が起きるのはしょうがない。要は、どう前向きに上手に付き合っていくかですよね。その辺りのバランスを、これから学んで行きたいなと思っています。
とりあえず随分良くなっては来たものの、まだ外を歩ける状態ではなく、ずっと座っているのも無理な状態なので、今日一日もう少し安静にしておくことにします。幸い月曜日、火曜日と、会社や客先と連絡を取り合いながら自宅で仕事を続けることができています。皆のサポートあっての事、ありがたいです。うまく行けば今週末には十分復帰できそうなので、急がず焦らず治して行こうと思っています。というわけで、またもや長い記事にお付き合いいただきありがとうございました。
それでは、今日も皆様良い一日を。
[ad#ad-2]