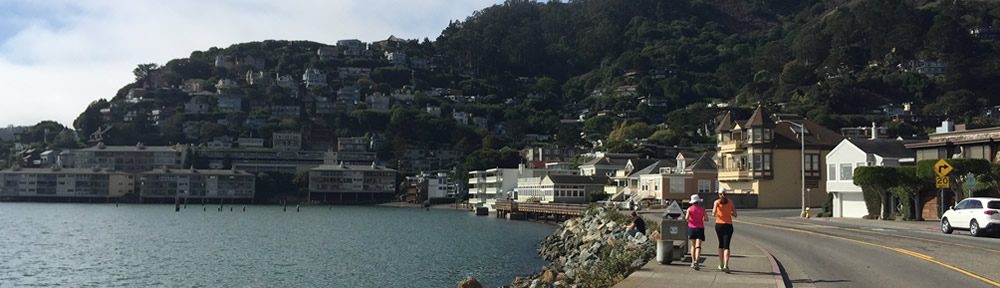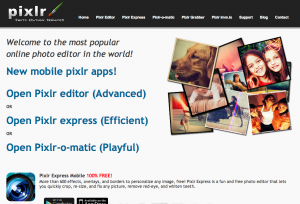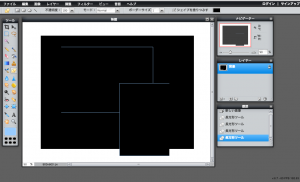・
昨日、理系の既卒者向けの企業説明会を開きました。
その中で話をした内容の一部を幾つかピックアップします。
当社は、革新的な製品を生み出し続けるテクニカルなITベンダーです。ここで働く人々は、エンジニア、プログラマ、デザイナー、マーケッターなど、それぞれ専門的な技術を持っています。テクニカルな会社と言うと、クールなイメージがあるかもしれませんが、私達は逆に、温かくて、礼儀正しく、親切で、誰にでも挨拶をすることを大切にしています。皆さんも、説明会のセミナルームに入る時、社員が元気よく挨拶してくれたのを見て驚かれたのではないでしょうか。デジタルな時代こそ、血の通った関係、相手の目を見て気持ちを伝える関係が大切だということを知っているからです。
・結果を出すこと、稼ぐこと。
当社は普通の枠組みで物を測りたくない会社です。
会社というのはこうあるべき、ビジネスマンというのはこうあるべき、という考えはあまりありません。もちろん、マナーや礼儀は重要ですが、それは「相手に対する気持ち」があれが誰でも出来ること。それよりも大切なのは「きちんと結果を出すこと」です。
自社の製品開発、サービス開発、受託案件でも、必死でやって結果を出す。それを続ければ会社は必ず成長します。そしてそこから繋がるのは 「徹底的に稼ぐこと」です。ですから、それ以外のことについては余りこだわりません。いくら格好いいことを言っても、美辞麗句を並べても、稼がなければビジネスをしている意味がありません。結果を出すために、もう一つ大切なことがあります。それは、「とにかくお客様目線であること」。成熟したこの時代、質の悪さ、適当な仕事は簡単に見破られてしまいます。つまり、結果が出ません、稼げません、お客様に喜んでもらえません。ですから、お仕事をさせていただいているクライアントさんからの要望には徹底的にお応えします。
枠にとらわれないこと。
世界を見渡した時に、出来るビジネスマンというのは会社名や肩書きではなく、�「僕は◯◯です」と名前で自分を自己紹介しますね。��つまり、自分は、自分なのです。僕はこういう仕事をしていたけれど、今勤めている会社ではこういう仕事をしています、という人がゴロゴロしています。��システムエンジニアから金融に行ったトレーダーもいますし、営業マンからエンジニアに転身した人間もいます。��つまり、自分はこういう人間だと決めつけてしまうと、そこからの成長もありませんし、思考が停止してしまって面白くない人生を歩んでしまうことにもなりかねません。��
会社も同じだと思っています。��うちはIT企業です、ソフトウエアベンダーです、Sierです。�分かりやすいのでそういうこともあります。�しかし、それって「今」の姿です。これだけ変化のスピードが速い時代、うちはこれです!ということに、果たして大きな意味があるのでしょうか。��当社のメンバーはITが大好きですし、お客様が喜ぶ顔が大好きですので、そこから大きく逸脱した会社になることはないかもしれませんが、将来的にどのように発展していくのかについては、決め付けないようにしています。
皆さんも、決して、決め付けないように。
これほど変化の速い時代、「自分はこういう人間で、こんなことしか出来ません」では誰も見向きしてくれなくなりますよ。そういう人間は他にも代わりがゴロゴロいるからです。そして、「マイペースで、無理せずに、」という言葉もあまりお薦めしません。先に言いましたが、これほど変化の速い時代、そんなことではいつまでたっても成長できず、あっという間に取り残されてしまいます。視野を広く持ちましょう。
5年で習得できることを1年で習得することは、脳から血が出るような、毎日毎晩吐きそうになる程のプレッシャーがあります。でも、一度そこを乗り越えてしまうと、後が楽。そこから先は、習得した知識とノウハウをベースに、自分でどんどん新しいものを自由に作っていけば良いのです。それでも、「いや、マイペースでコツコツがんばります」という人は、はなくそでもほじっていてくださいね、ということになってしまいます。
全員精鋭主義
少数精鋭ではありません、全員精鋭主義です。 これには各分野、職務においてプロフェッショナルでいることが 求められます。野球チームを思い出してください。それぞの打順、ポジションで最大限のパフォーマンスを発揮することでチーム一丸となり、勝利という果実を得ることができます。誰かがサボってしまうと、チームは負けてしまいます。全員力で勝つチームを目指しています。
主体性と当事者意識
「主体性」とは、「自分の意志・判断によって、みずから責任をもって行動する態度のあること。」と定義されています。指示を待つ、環境が整えられるのを待つという姿勢は、主体的ではありません。受動的です。受動的な人間は言い訳をしますし、環境のせいにします。「俺がヒットを打てなかったのは、観客のヤジのせいだ!」という人間に一流の選手がいるでしょうか?自分の意志で、責任を持って行動することで、道は切り開かれます。
MITメディアラボの石井教授のこの記事を読んでみてください。
当事者意識とは、”何らかの物事やプロジェクトなどに参加している当事者である、関係者である、という意識のこと”と定義されています。この意識がないと、他人任せになってしまい、自分の事は棚に上げ、誰かがやってくれるだろう、という意識が芽生えてしまいます。 ということで、辛いこともたくさんありますが、楽しいこともそれ以上にたくさんあります。この辺りは働く社員達の表情を見て感じ取ってください(説明会の間、会議室のパーテーションはあえて開けっ放しにして、ガラス越しにワークスペースが見えるようにしていました)。