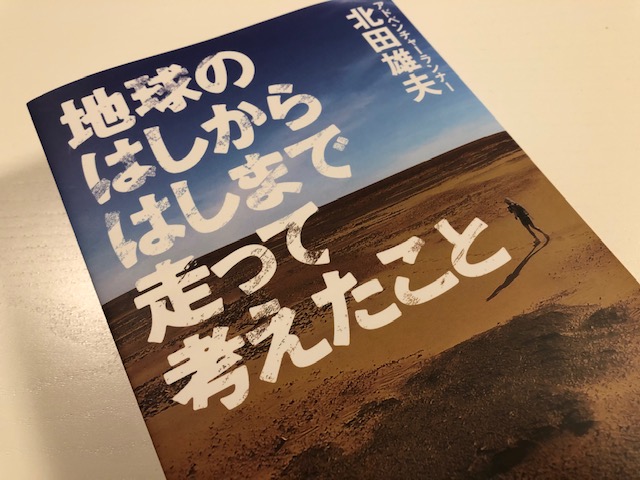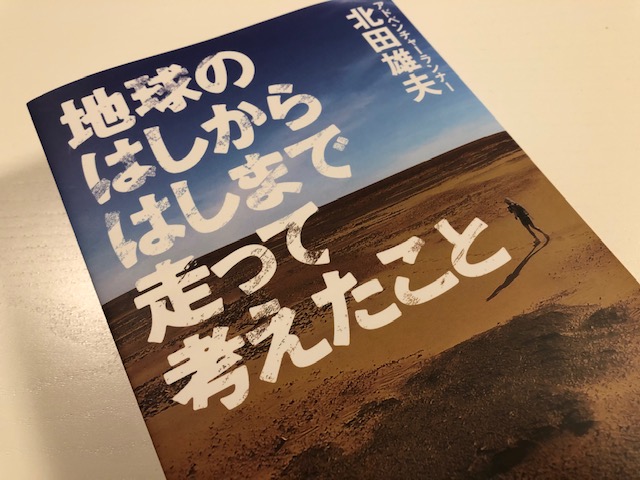挑戦。
当たり前のように聞く言葉だが、「挑戦」とはなんだろう。その言葉の本当の意味を考えたことがあるだろうか。そして、仮にその言葉の意味を知った時、自分は何かに「挑戦」したことはあるだろうか。
「地球のはしからはしまで走って考えたこと」は、日本で唯一のプロアドベンチャーランナー・北田雄夫さんが世界七大陸アドベンチャーマラソンを走破し、その後も次々と前人未到のレースに挑戦していくライフストーリー。情熱大陸(毎日放送)を見て、知っている人もいるかもしれない。
この本を読んでいると、まるで自分が実際に走っている気持ちになるから不思議だ。
飛行機に乗り、空港で荷物をピックアップし、宿泊施設で荷物をほどき、足りない物は現地で購入し、世界中から集まるが、数は決して多くないアドベンチャーランナーたちと交流する。自分も一緒にゴビ砂漠を走り、南極の雪に足を取られながら進み、サハラ砂漠の暗闇の中を祈るような気持ちでルート取りをしているような気持ちになる。まさに今ここが「その場所」であるかのような錯覚に陥る。
アドベンチャーマラソンは、一種のハイテンションな、アドレナリンが爆発するようなエクストリームスポーツのようにイメージするかもしれないが、実は真逆なのだと思う。
基本的にアドベンチャーマラソンでは、寝具や薬、食料、その他必要なものはすべて自分で背負って走る。一日の消費カロリーを計算して、摂取カロリーの分だけ食料を用意する。荷物は1gでも軽い方がいいので、緻密に重量を計算しながら、持参物も食料も選択していく。飽きてはいけないので、食べ物の種類にも気を使う。寒暖の差に耐えれるように、ウエアは素材から吟味する。
もはや勇気さえあれば「えいやー」で挑めるようなものではなく、深い洞察と経験値がモノをいう世界なので、40代、50代のベテランランナーが多いのも頷ける。感覚というよりは、数学。そして、生きる力、精神力。そういう世界なのだ。
挑戦という言葉を考えた時、北田さんの前人未到のチャレンジから学ぶことはたくさんある。普段の生活の中で、誰もが「選択」と「決定」を繰り返している。その中には、自分にとって挑戦(=チャレンジ)と思えるような選択もある。一歩踏み出すには確かに勇気がいる。
ただ考えてみると、自分の場合は、ある程度「見える景色」の中で勝負しているのではないか、と思うこともある。まったく先が見えない、前例がない、ひょっとしたら命を落とすかもしれない、そんな見えない景色をあえて見に行こうとしているだろうか。リスクヘッジをしながら、言い訳をしながら、逃げ道を探しながら生きてはいないだろうか。
新型コロナウイルスで、様々な制限があり、心身ともに停滞気味の人も多いだろう。でも、その中でも出来ることはたくさんある。前に進めば、風景が変わり、一歩登れば、景色が変わる。
普通の人でも、挑戦はできる。
そして、挑戦することで、また世界が変わる。人生が豊かになる。
走る人も、そうでない人も。すべての人にオススメの一冊です。