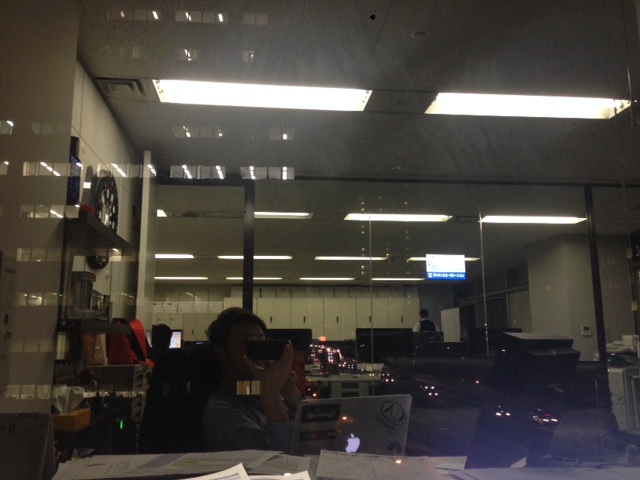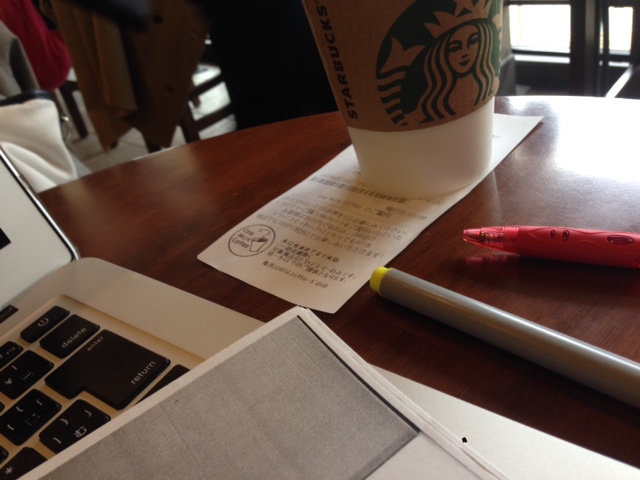・
毎年6月は本ブログの誕生月。
この時期には、この一年と今まで積み上げてきた年月の振り返りをすることが多くなります。
一回目の記事を投稿した2005年6月10日、当時僕は29歳、長女は生後6ヶ月の赤ちゃんでした。あれから書き続けて丸10年が経過し、11年目に入りました。長女の年齢とブログの年齢がほぼ同じなので覚えやすいですね。小学生でいうと5年生。娘もブログも大きくなったなあ、としみじみ実感します。

・
ブログを書く目的と、書き続けてよかったなと思うことは年月を経てもあまり変わりません。一年前に書いた記事を読むと、ブログを書く目的について上手にまとめていることに気づきました。幾つか文章を抜粋しながら、リライトしてみます。
書く内容は年齢によって変化しているようです。仕事の領域も行動する範囲も随分と広くなったと思いますが(一年に4回もアメリカと日本を往復するなんて10年前は考えられなかった)、変に「こなれた感」と「くたびれ感」があり、昔の勢いや、尖った気持ちや、若さゆえの「無敵感」などは最近全く衰えてしまいました。たまに昔のエントリーを読み返すこともありますが、アツ苦しい事を書いていたりするのを見ると、ああ、もっと頑張らないとな、もっと攻めていかないとなと思うことも多いです。
僕にとってブログを書くことは、一日一日を丁寧に塗りつぶすこと。
時間に流されたり、目先の事に追われて、ただ漫然と日々を過ごすということだけは避けたくて、一日一日を丁寧に塗りつぶすということだけはずっと意識しています。その他の目的は、備忘録であったり、反省であったり、ニュースのレビューであったり。
その日に何を感じ、何を考えたのか。それを記録として残すこと、そして書くことによって考えを整理すること。聞いたことや学んだことをアウトプットすることで、インプットした情報がメモリーされるので、書いたことは良く覚えています。そう考えると、少なくとも、書くことによる悪い影響はなかったかな。出来る限り毎日書くことを自分にコミットすると、常にインプットを意識することになります。インプットした情報を頭の中で整理して、書く。この作業が習慣化しているので、伝える、書くということに抵抗はありません。
「習慣化」というのは、自分の中で大きなキーワードです。特別なスキルも才能も持たない人間にとっては「コツコツと積み上げること」が唯一成長するための手段だと思いますし、そのためには習慣化することが必要です。でも実際「言うは易し、行うは難し」で、習慣化するのって結構大変だったりします。まず面倒くさい。仕事や学校ならまだしも、人から「やれ」とも言われていないことを、自分で勝手に決めて行うことに何の意味があるのか。しかも、ほぼ独り言。面倒くさいなー思うことも多々ありました。
そのハードルを乗り越えるためには「その事を好きになる」ことが一番早いですよね。好きになれば勝手にやる。これは仕事も同じで、やっていることを好きになると(ジョブズは「好きなことを仕事にしなさい」と言っていますが)、人間って勝手に動くものです。義務命令ではなく、能動的かつ積極的に動く。そういうものだと思って、今まで続いています。
自分が始めた当初は、ちょうどブログが流行り始めた頃で、みんながFC2やアメブロやライブドアブログなどで書き始めていた頃です。今はその中の何割の人が残っているのか分かりませんし、無料ブログ=アフィリエイトという要素が強いので、拙ブログのような何の利益も生まない(むしろドメインやサーバ代などで赤字)、本当の意味でのプライベートブログは段々と数が減ってきて、SNSのタイムラインに移行している訳ですが、これから益々「個の時代」が加速すると、特定の企業が提供するSNSプラットフォームではなく、独立したプライベートサイトやプライベートブログが、逆にどんどん増えてくるような気もしています。
そのように時代が変わったり、流行り廃れがあるかもしれませんが、いずれにしても、僕はここで、これからも何かを書いていくつもりです。
という訳で長くなってしまいましたが、11年目に入った「analog-web」。
これからも、ゆるくお付き合いくださいませ。