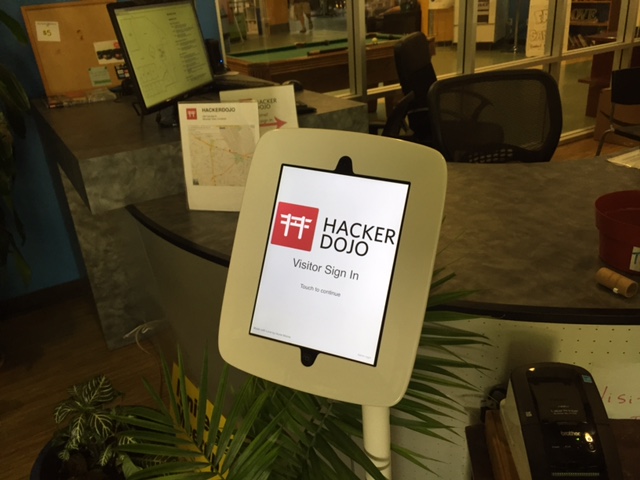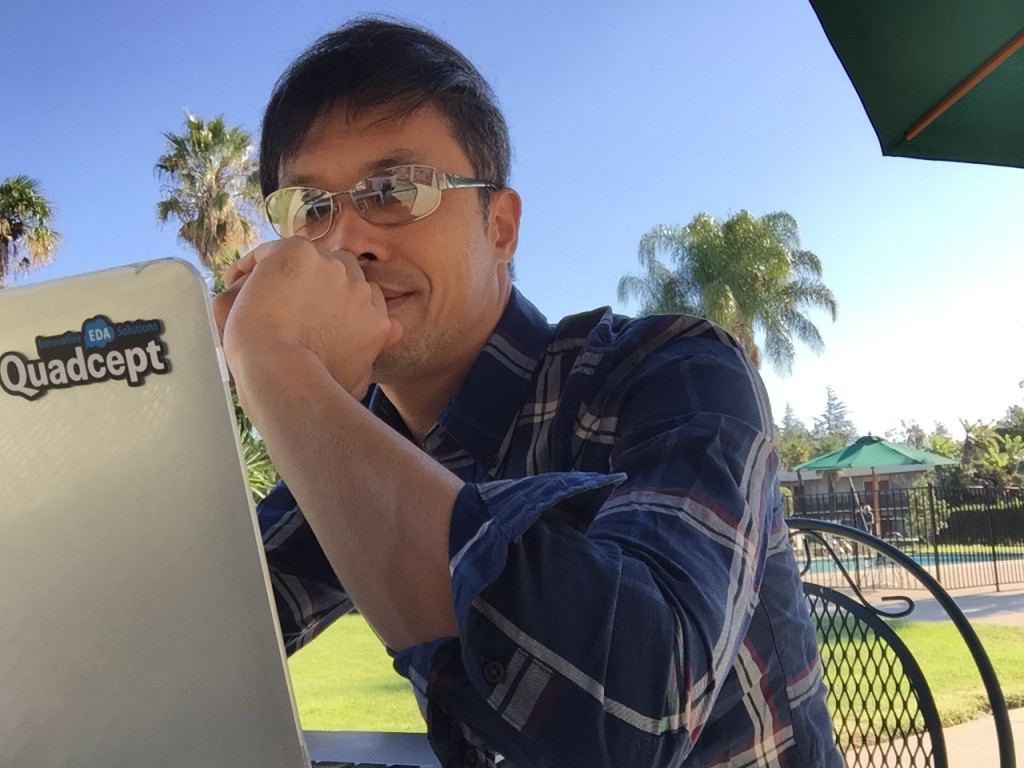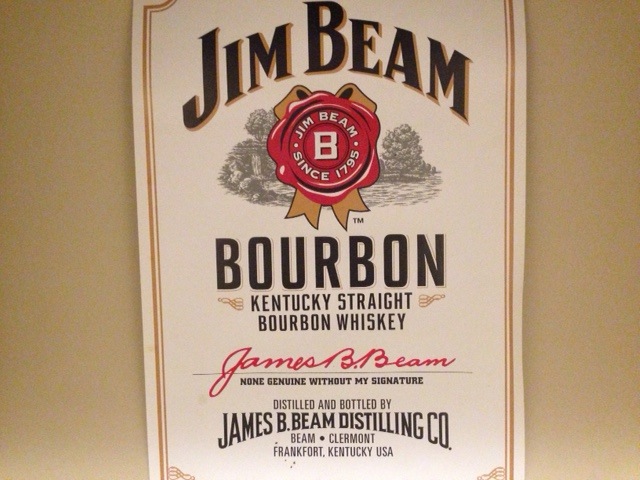・
Silicon Valley の Mountain View という場所は、Google本社とモフェットフィールドがあることで有名ですが、ここに「Hacker Dojo(ハッカー道場)」というシェアオフィスの機能も兼ね備え、各国からたくさんのエンジニアやデザイナーが集まり、日々研鑽を重ねている Tech Hub があります。
こちらのパートナー様の紹介で中に入れていただく機会をいただき、ちょうど日本からインターンに来ている学生さんを含めて、ジョインしておられる日本人エンジニアの皆様にもQuadceptを紹介させていただきました。
中は天井が高くてとても広く、遊び心があってお洒落でいかにもシリコンバレーのオフィスという感じ。フリーアドレスでたくさんの方がPCに向かって仕事をしています(詳細は Hacker Dojo のサイトをご覧ください)
Googleキャンパスも近いので、Chromeカラーに塗られたGoogle自転車も置いてあり、企業、個人、学生問わず、人と情報が垣根なく自由に行き来できているオープンな環境であることを垣間見ることができます。
車で走り回っていると、雄大な自然や低層階の建物、緑多い公園など、高速道路の渋滞を除いてはとても穏やかな場所のように見えるシリコンバレーですが、やはりここは、IT、TECH、ものづくりの分野で世界を牽引する企業群とスタンフォードのような大学を中心とした巨大なエコシステムが世界中から人と物と情報を集め、また、それがゆりかごの役目を果たし、このような Tech Hub から、次の時代を担う若者達、新しいスタートアップスがまた続々と生まれるんだなと思うと、あらためてこの地域の凄さを感じます。
それと同時に、英語が苦手な日本がなぜここまで成長できたのか、なぜ今でも世界三位の経済大国として君臨して続けていられるのか、逆にそれはすごいことなのではないのかとも思います。
年に二、三回は訪れている場所ですが、いつ来ても色々と考えさせられる場所です。